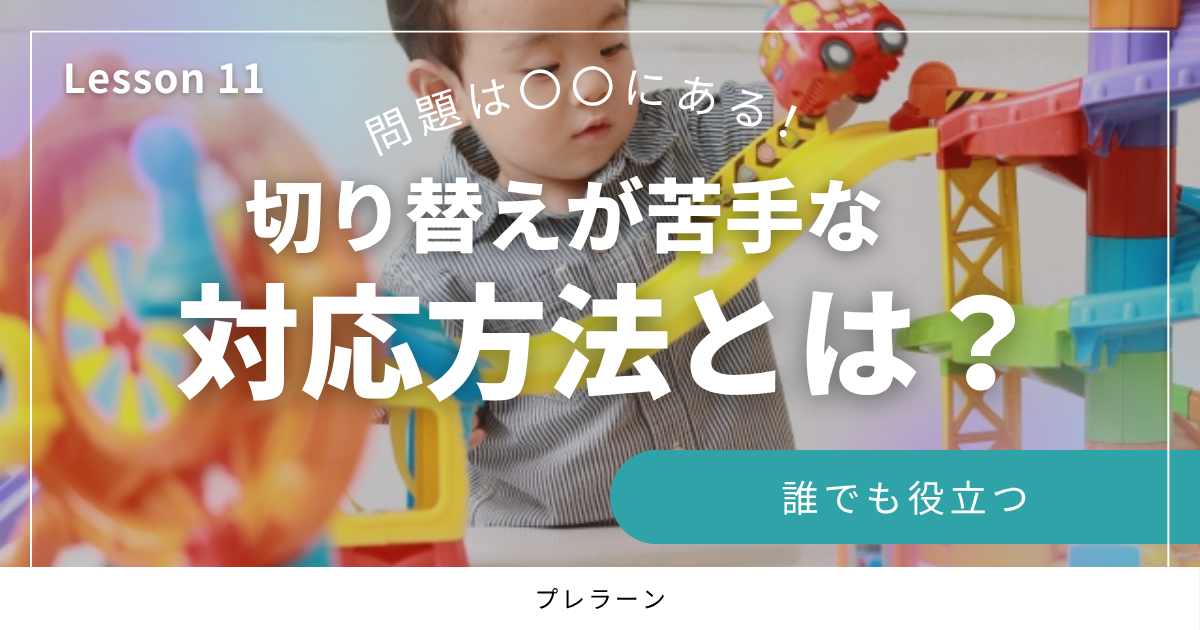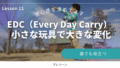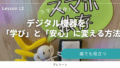はじめに:「もう終わり!」「まだやりたい!」その気持ちの裏にあるもの
放課後等デイサービスでよくある場面――
「もうすぐ活動の時間だよ」と伝えた途端に不機嫌になる、遊びを終えられず癇癪を起こす、片付けを拒否して動かなくなる…。
このような“切り替えの難しさ”は、発達に特性のある子どもにとって大きな課題の一つです。
でもそれは、「わがまま」でも「反抗的」でもありません。
“心の準備”が追いつかない状態だったり、“次に何が起こるか”が不安で仕方ないという状態なのです。
この記事では、「切り替えが苦手な子」に対する具体的な支援の工夫や声かけのポイントをご紹介します。
なぜ切り替えが苦手になるのか?

切り替えの難しさの背景には、主に以下のような要因があります:
■ 見通しの立てにくさ
→ 今やっていることが「いつ終わるか」「次に何をするか」が分からないと、不安になりやすい
■ 楽しいことをやめる“納得”ができない
→ 好きな遊び・活動をやめることに強い抵抗を感じる
■ 感情のコントロールが難しい
→ 急な切り替えで、気持ちの整理が追いつかず、パニックになる
■ 順序立てて考えることが難しい
→ 頭の中で「次の行動」への切り替えがうまくできない
このような“脳の働き方”に寄り添った対応が求められます。
放デイでできる切り替え支援の工夫5選
1. ■ 見通しを「見える化」する
- 絵カードやタイムスケジュールを使い、「今→次→その次」の流れを提示
- 時計やタイマーを活用して「あと何分」を具体的に伝える
2. ■ 「予告」をして心の準備をつくる
- いきなりの声かけではなく、「あと5分したらお片付けね」と予告型の声かけを心がける
3. ■ “楽しいことの後に楽しいこと”でつなぐ
- 「終わったら〇〇しようね」と、“終わり”ではなく“次の楽しみ”を提示する
- 遊び→おやつ、活動→ごほうびなど、メリハリをつけて誘導
4. ■ 子どもが選べる選択肢を用意する
- 「お片付け、どっちの袋からやる?」
- 「次は本読むか、お絵かきか選んでね」
→ 自分で決めることで“切り替えやすく”なる
5. ■ 終わる理由を納得できるように伝える
- 「みんなが使うからね」「次に大事なお仕事があるから」など、納得のいく理由づけを添えて説明する
切り替え失敗時の対応:感情の爆発にどう向き合うか
- まずは安全を確保し、無理に動かそうとしない
- 落ち着いてから「〇〇が嫌だったんだよね」と気持ちの代弁をする
- 感情が落ち着いたあとに、「今度はこうしようね」と次につなげる声かけを意識する
切り替えの失敗は“成長のきっかけ”。
次に活かせる支援を心がけることが、安心につながります。
保護者と連携して“切り替えパターン”を共有する
- 家庭での切り替えの様子を聞き取り、支援に活かす
- 放デイで成功した方法を家庭でも伝える(例:「〇〇の後に好きなことを伝えると動きやすかったです」)
- 「失敗した時の対応」も共有し、一貫した支援方針をつくる
保護者との連携が、子どもにとっての“安心と予測可能な環境”を整えるカギになります。
まとめ:「切り替えられる子」より、「切り替えやすくなる支援」を

切り替えの苦手さは、「本人の問題」ではなく、環境や関わり方で大きく変わる特性です。
支援者に求められるのは、「どうやって気持ちを整えるか」「どうやって安心して動けるようにするか」を一緒に考え、支えること。
“できない”ことを責めるのではなく、“どうすればできるようになるか”を一緒に見つけていくことが、信頼と成長をつくる支援です。
今日の切り替えの中にも、必ずその子なりの“頑張った一歩”があるはず。
それを見つけて、支えていける放デイ支援をこれからも積み重ねていきましょう。