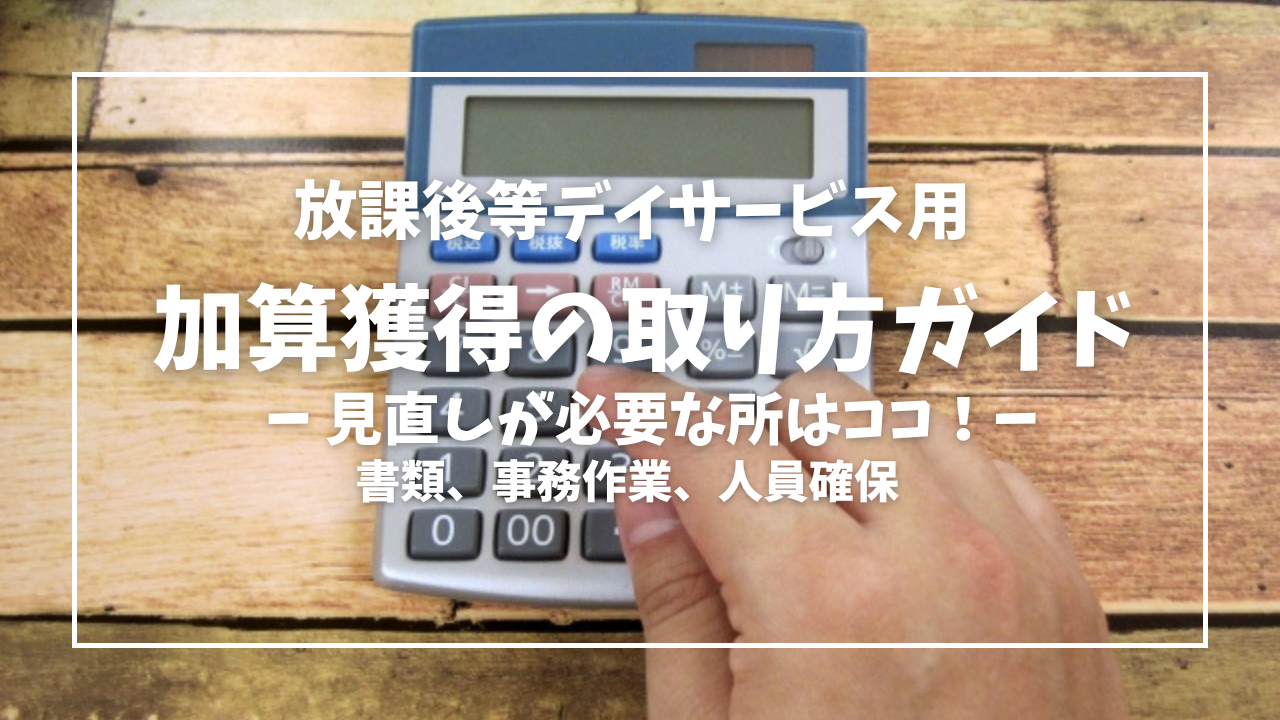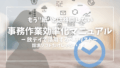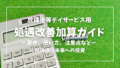はじめに:加算は「狙って取る」時代へ
放課後等デイサービスの運営において、「加算」は単なる“おまけ”ではなく、事業の継続と質の向上を支える重要な収入源です。
加算を「取りこぼしている」「取れているけれど不安定」という声も多く聞きますが、今や“戦略的に加算を取りにいく”ことは、施設運営において必須です。
この記事では、加算の基本から具体的な取得戦略までを、わかりやすく整理してお伝えします。
加算制度の基本と放デイにおける意味

加算とは、基本報酬に上乗せされる「条件を満たした施設に対する報酬」です。
放デイにおける主な目的は次の通りです:
- 利用者の多様なニーズへの対応を評価
- 質の高いサービス提供体制を維持
- 職員の配置や研修の充実を促す
つまり、加算はただの「収入増」ではなく、**より良い支援の循環を作る“制度的インセンティブ”**とも言えます。
よくある加算の種類と条件一覧(主要加算解説)
| 加算名 | 主な条件 | ポイント |
|---|---|---|
| 児童指導員等加配加算 | 児童指導員または保育士を追加配置 | 常勤・資格要件・シフト調整に注意 |
| 福祉専門職員配置等加算 | 社会福祉士や精神保健福祉士を配置 | 就労支援型では特に重要 |
| 医療連携体制加算 | 看護職員配置、個別支援計画に医療的配慮がある場合 | 通院支援が多い場合は必須級 |
| 保護者支援加算 | 定期的な面談や家庭支援活動の記録 | 支援会議や家庭訪問と連携可能 |
| 個別機能訓練加算 | 作業療法士などによる機能訓練の提供 | 療育型に特化する場合に相性良し |
※細かい運用要件は都道府県通知・指定基準に準拠
上手に加算を取るための3つの考え方
① 「取れる加算」より「取り続けられる加算」
一時的に無理をして取得しても、体制が維持できなければ減算や返金リスクに。“持続可能性”のある体制設計が大前提です。
② 現場と連携した“日々の仕組み化”
加算の証拠となる記録・業務は、**現場スタッフが自然に行える形で“ルーチン化”**しましょう。教育と仕組みづくりが鍵です。
③ 記録・証拠・運営体制の整備
加算は「やっている」だけでは不十分。“やった証拠が明確に残っている”ことが求められます。定期的な内部点検を忘れずに。
加算取得の成功例と失敗例
◎ 成功例:加配加算+保護者支援加算の連携運用
「児童指導員の増員」と「保護者との面談記録」の運用を連携し、支援の質と報酬の両立を実現。
✕ 失敗例:医療連携加算の書類不備による返還
必要書類の一部記載漏れにより、全期間の加算が否認されたケース。定期的な第三者監査が推奨されます。
加算獲得のための年間スケジュール管理術
| 時期 | 対応内容 |
|---|---|
| 4月 | 新年度加算計画・体制届出、職員体制整備 |
| 6月〜8月 | 研修計画の実施・実績記録 |
| 10月 | 記録様式の見直し、ミス防止策の導入 |
| 12月〜2月 | 監査対策・自己点検 |
| 年度末 | 実績報告・来年度の加算戦略検討 |
加算管理は“年間を見通したPDCA”がカギです。
よくある質問(Q&A)
Q. 加算の算定基準がよく変わるので不安です…
→ 都道府県や市町村の最新通知を定期チェックし、行政との関係を密にしておくと安心です。
Q. 体制が整っていないので、加算を諦めています…
→ 一気に全加算を取る必要はありません。「まず一つ、確実に取れる加算」から着手しましょう。
Q. 記録が煩雑でスタッフの負担が大きいです…
→ 業務支援ソフトや記録テンプレの導入、ICTの活用で業務負担は大きく軽減できます。
まとめ

加算は“知っているかどうか”より、“戦略的に運用しているかどうか”が明暗を分けます。
- 取りやすい加算から無理なくスタート
- 日々の記録や体制整備をルーチン化
- 持続可能な仕組みで「取り続けられる状態」をつくる
加算は収入の柱であり、支援の質を高めるためのツールです。攻めと守りのバランスを大切に、「健全な運営」を実現しましょう。
CTA(行動喚起)
まずは自施設で「今、取れている加算」「今後取りたい加算」を“棚卸し”してみませんか?
小さな見直しが、経営の安定と支援の質向上につながる第一歩になります。