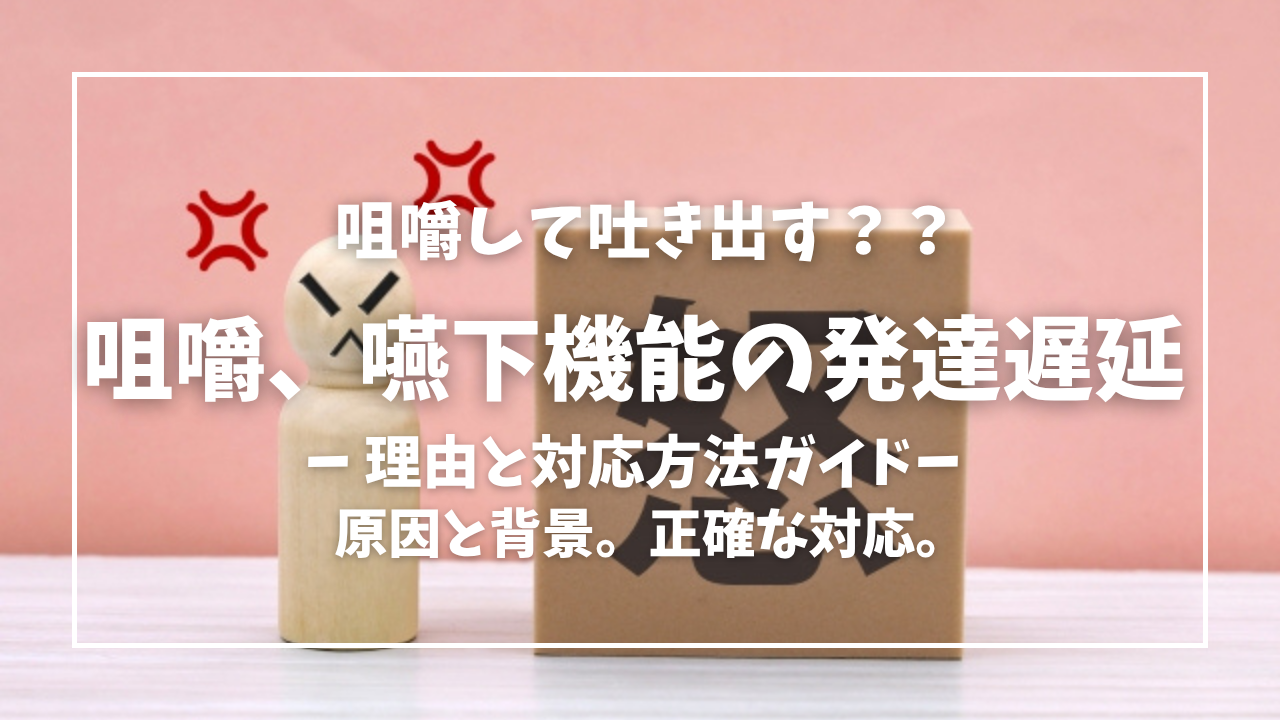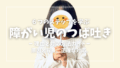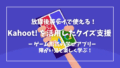1. はじめに:なぜこの行動が注目されるのか?
障がいのある子どもが「一度咀嚼して口に含んだまま吐き出す」という行動は、しばしば不衛生である一方、その背景には発達段階や摂食嚥下機能の発達過程に起因する場合が多くあります。適切に理解し対応しなければ、誤嚥リスクや衛生問題、支援者のストレスにもつながります。
2. 咀嚼後に吐き出す行動の背景・原因

2.1 摂食・嚥下機能の発達遅延や不安定さ
- 発達段階では、咀嚼と嚥下が別々に学習され、順調に進まない場合、一度咀嚼して吐き出すという行動が見られることがあります。
2.2 感覚過敏・感覚探索行動
- 感覚処理に差がある子どもでは、噛んだ後の食感や味の変化を確認することで安心を得ようとする傾向があります。
2.3 行動の機能的目的(逃避・注目)
- 食べるのを嫌がる不快や味への抵抗、あるいは注目を得るためにこの行動を用いることがあります。発達障がい児の「嚥下円座行動」などには、こうした機能保持が含まれます。
3. 潜在的リスクと支援上の課題
- 衛生・感染:床や机に吐き出された食物に細菌が付着しやすく、清掃や衛生管理が必要です。
- 誤嚥・窒息:吐き出す前に顎の動きだけで一部を食塊化してしまうリスクがあるため要注意。
- 食事の遅延・栄養欠乏:口に含んで吐き続ける時間が長くなると食事進行に影響し、摂取量が不足する恐れがあります。
4. 支援現場での対応ステップ
4.1 状況の記録とパターン分析
- 吐き出すタイミング、食形態、環境(誰と・どこで・何を食べているか)を詳細に記録し、行動に先行・結果する要因を分析します。
4.2 感覚環境の調整
- 食材の形態(ペースト・小片)や硬さを調整し、口腔内での扱いやすさを工夫します。咀嚼–嚥下へのスムーズな移行を促す食支援が有効です。
4.3 安全な代替行動の導入
- 噛むことは維持しながら、そのまま飲み込める習慣をつくる。バンゲード法など嚥下促進訓練を取り入れるのが効果的。
4.4 褒めて強化する
- 正しく咀嚼し、飲み込めた場合はすぐに肯定的な強化(言葉・シールなど)を行い、好ましい行動を増やします。
4.5 環境整備:衛生管理と安全確保
- 吐き出しやすい位置には容易に拭ける素材を使用し、必要に応じて手袋やマスクで衛生面を強化します。
4.6 多職種の連携と家庭共有
- 言語聴覚士や作業療法士とも連携し、家庭と現場での対応を統一化。「できたら○○をする」という共通理解は支援の安定につながります。
5. 食形態・食支援の具体例
- トロミ調整や一口量をコントロールすることで、嚥下が容易になり、咀嚼して吐き出す行動が減りやすくなります。
- バンゲード法(口唇・顎の補助)による嚥下促進は、「口から食べる」アクションを習慣化する支援として有効です。
6. 支援者の視点:成果とモニタリング
- 月次スタッフ会議で状況共有し、記録データをもとに支援方針を評価・改善していきます。
- 記録表には「内容・形態・反応・量・時間」を記録し、変化をチェックします。
✅ まとめ:支援フロー・チェックリスト
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 記録 | 「何を」「どこで」「どうした」を詳細に記録 |
| 2. 原因分析 | 感覚・環境・機能的背景を分析 |
| 3. 食材調整 | 固さ・形態・量の調整 |
| 4. 嚥下促進 | バンゲード法やペースト形態導入 |
| 5. 行動強化 | 成功時は即褒め・報酬を与える |
| 6. 衛生対応 | 吐き出し場所の清掃・衛生対策を徹底 |
| 7. 連携調整 | ST, OT, 家族と共通の支援方針 |
| 8. モニタリング | 月次・PDCAで支援内容見直し |
📌 最後に

咀嚼後に吐き出す行動は、多くの場合に発達や感覚的な背景があり、単なる“悪癖”ではありません。食支援の視点から段階的かつ丁寧にアプローチすることで、咀嚼と嚥下の連結が促進され、安全かつ衛生的に食事を取る力につながります。保護者・支援者と連携しながら、丁寧な支援をご一緒に進めていきましょう。