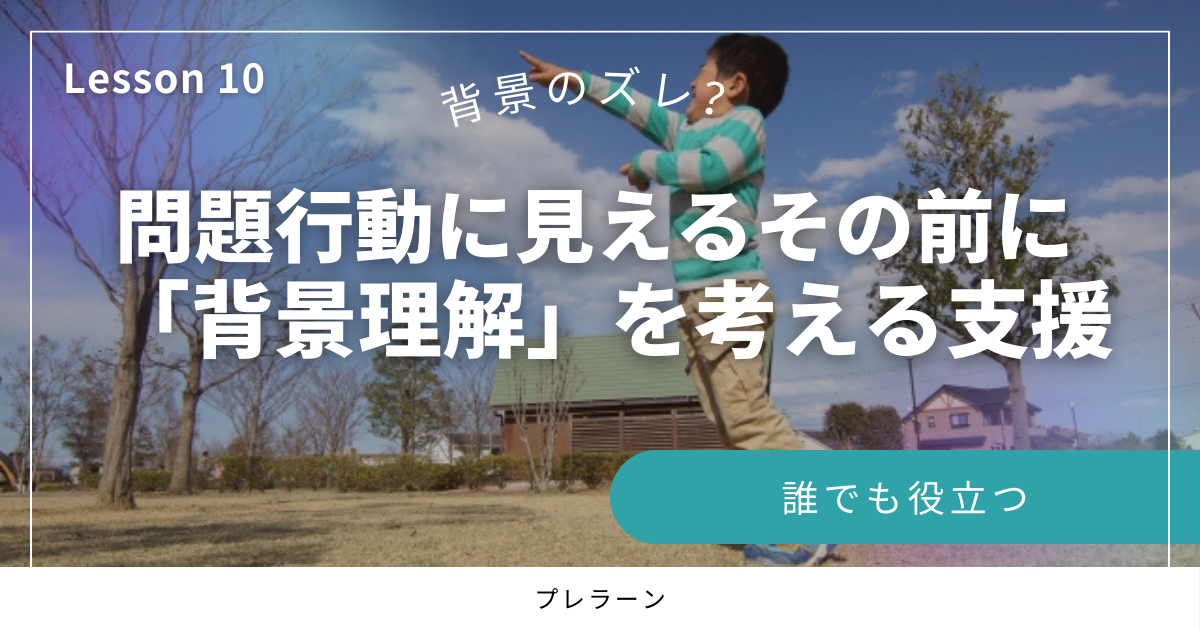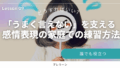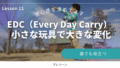はじめに:問題行動の“奥”にある気持ちを見つめよう
「物を投げた」「叩いた」「叫んだ」「逃げた」――
放課後等デイサービスで支援にあたっていると、こうした“問題行動”に頭を悩ませることがあります。
でも、それらの行動は、子どもがわざと迷惑をかけようとしているわけではありません。
むしろ「困っている状態」や「助けてのサイン」であることがほとんどです。
この記事では、問題行動がなぜ起こるのかを理解し、叱る前にできる支援の工夫をご紹介します。
問題行動の正体は「表現のズレ」
子どもたちは、まだ言葉や行動で自分の気持ちをうまく伝える力が育ちきっていません。
そのため、
- イライラして物を投げてしまう
- 注目してほしくて騒ぐ
- 予定変更に混乱してパニックになる
など、「別の形で伝えようとして失敗している」ことが多いのです。
つまり、問題行動は“気持ち”と“行動”のミスマッチ。
そこに支援者が気づけるかどうかで、対応が大きく変わります。
問題行動を減らすための5つのアドバイス

1. ■ 原因を探る「観察力」を持つ
- 行動の前にどんな“きっかけ”や“環境要因”があったかを確認
- 例:「音が大きかった」「急に予定が変わった」「相手の言葉がきつかった」
問題行動の“前”を見つめる視点が、支援のヒントになります。
2. ■ 予防的な環境調整を行う
- スケジュールを見せて見通しを持たせる
- 静かなスペースを用意する
- 使いやすい言葉・伝え方を事前に教えておく
環境が落ち着いていれば、問題行動の頻度はぐっと減らせます。
3. ■ “してほしい行動”を教える
- 「ダメ!」だけで終わらず、「こうしてくれると助かるよ」と具体的な代替行動を教える
- 例:「大きな声じゃなくて、先生に“ちょっといいですか”って言おうね」
禁止ではなく“指針”を与える支援が、子どもを前向きにします。
4. ■ 落ち着いた後に“振り返り”の時間を持つ
- 感情が落ち着いたタイミングで、「さっき、どんな気持ちだった?」とゆっくり振り返る
- カードやイラストを使って感情を整理するのも効果的
支援者と一緒に考えることで、次の行動が変わります。
5. ■「できたとき」をしっかり認める
- 問題行動を減らすだけでなく、“いい行動”ができたときにしっかり褒めることが大切
- 「今、ちゃんと順番待ちできたね!」「ありがとうって言えたね、すごい!」
ポジティブな声かけは、良い行動を“定着”させる力になります。
問題行動を「悪」と捉えない視点が大切
- 怒られることでしか関われなかった
- ダメって言われることでしか注目されなかった
そんな経験を持つ子どもほど、「問題行動=唯一の表現手段」になってしまっていることがあります。
支援者に求められるのは、行動そのものではなく、“行動の背景”に寄り添う姿勢です。
「どうしたかったのかな?」「なにが難しかったのかな?」と考えることが、信頼関係を築く第一歩になります。
保護者と協力して問題行動の対応をそろえる
放デイだけの対応では、なかなか改善が見られないこともあります。
だからこそ、保護者との情報共有・方針共有が大切です。
- 家庭での様子をヒアリングする
- 放デイでの対応方法を分かりやすく伝える
- 「ご家庭ではどう関わっていますか?」と協力を呼びかける
支援の方向性を“チーム”でそろえることで、子どもも安心して行動できるようになります。
まとめ:「行動を減らす」のではなく、「困りごとをなくす」支援を

問題行動をただ「なくそう」とする支援は、一時的にはうまくいっても、根本的な課題解決にはつながりません。
大切なのは、「なぜその行動が出たのか?」を見つめ、困り感を減らす支援を重ねていくことです。
叱る前にできること。
伝える前に整えられる環境。
見逃さずに届けられる“できたね”の言葉。
その一つひとつが、子どもを変え、支援者との信頼を深めていきます。