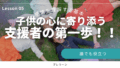はじめに:「自立」とは、できるだけ“ひとりで”じゃない
「自立支援」と聞くと、「できる限りひとりでできるようにすること」と考えがちですが、
本来の“自立”とは、自分の意思で行動を選び、必要なときに助けを求められる力を育てることです。
障がいのある子どもたちも、自立の力を少しずつ育むことができます。
それは決して特別な訓練ではなく、日常の関わり方や支援の中にある小さな積み重ねで実現していけるのです。
この記事では、「自立」に向けて放デイ支援者ができる具体的なアプローチをご紹介します。
自立とは何か?:3つのキーワードで整理する

1. 【選ぶ】
自分で「これがいい」と決めることが自立の第一歩。
たとえ2つの選択肢でも、「自分で選んだ」経験が子どもの意欲を育てます。
2. 【やってみる】
うまくできなくても、「やってみる」ことに価値があります。
支援者は、“完璧さ”ではなく“挑戦する気持ち”を尊重しましょう。
3. 【助けを求める】
「手伝って」「分からない」と言える力も、大切な自立スキルです。
支援者が日ごろから“助けを求めやすい関係性”を築くことが土台になります。
自立を育むための5つの支援アプローチ
1. ■ 見通しを持てる環境づくり
やるべきことが曖昧だと不安が増し、自分から動けなくなってしまいます。
・絵カードやスケジュール提示
・手順を1つずつ示す“分かりやすさ”の支援
2. ■ できることから“任せる”
「これお願いしていい?」と簡単な役割を任せることで、
「自分にもできる」という自己効力感が育ちます。
→ 例:おしぼり並べ/荷物を持つ/人数を数える など
3. ■ 成功体験を“言葉にして返す”
子どもが何かをやりきったときに、「できたね!」「一人でやれたの、すごいね」と言葉でしっかり伝える。
→ これが“自立の自覚”を生み出します。
4. ■ 自立を「ひとりでやらせること」と思わない
失敗しても「大丈夫だよ」と一緒にやり直す関わり方が、「次は自分でやってみようかな」のきっかけになります。
5. ■ 自分の気持ちを伝える手段を持たせる
ジェスチャーや絵カード、キーワードだけでもOK。
意思表示の練習は、「自立の入り口」であり、「人と関わる力」を育てる支援です。
放デイでできる“自立支援プログラム”の例
- 朝の会で「今日の役割を自分で決める」
- クッキング活動で「自分の分を自分で作る」工程を体験する
- 片付けや整理整頓を“マイチェックリスト”で管理する
- 帰りの支度で「自分でランドセルを確認」する習慣を育てる
どれも、特別な教材や訓練は必要ありません。
日常の中に“できることを増やすチャンス”は無限にあります。
保護者との連携が「自立支援」を加速させる
家庭と放デイ、それぞれでバラバラな支援をしていては、子どもも混乱してしまいます。
支援者は、「家庭でもできそうなこと」を提案し、保護者と以下のような連携を図ると効果的です。
- 支援の工夫や声かけのポイントを共有する
- 「こう言うとやる気が出ていましたよ」と、保護者が取り入れやすい言葉がけを伝える
- 家庭で頑張っている様子も、放デイでしっかり褒めてあげる
自立は、“子どもを一人にすること”ではなく、“周囲とつながりながら成長していくこと”。
だからこそ、大人同士のチーム連携が何より重要です。
まとめ:「自立」とは、“一人で”じゃなく“ひとりの人として”育てること

障がいのある子どもにとっての自立とは、「すべて自分でできるようになる」ことではありません。
むしろ、「自分で選び、やってみて、必要なときに助けを求める」そのプロセスを支えることこそが、本当の自立支援です。
支援者が子どもを信じて、小さな「できた!」を一緒に喜ぶこと。
それが子どもの自信となり、自立への一歩となります。
今日の関わりの中にも、きっと“自立につながる瞬間”があるはずです。
その一つひとつを見逃さず、育てていく関わりを、これからも大切にしていきましょう。