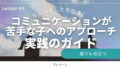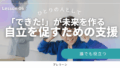はじめに:行動の裏にある“感情”を見つめていますか?
放課後等デイサービスで働いていると、子どもが突然怒り出したり、泣き出したり、黙り込んでしまうことがあります。
そんなとき、「何がいけなかったんだろう?」と戸惑った経験がある方も多いはずです。
でも実は、こうした行動の根底には、その子なりの「感情」が必ず存在しています。
支援者が感情を理解することで、対応は大きく変わり、子どもとの信頼関係も深まります。
この記事では、放デイ支援において「感情」をどう捉え、どう支援につなげるかについて実践的に解説します。
子どもの感情は“未完成”で“繊細”

子ども、とくに発達に特性のある子どもたちは、感情をうまく整理・表現する力がまだ育っていないことが多いです。
そのため、「怒る」「泣く」「叫ぶ」「黙る」などの行動として、感情が一気にあふれ出てしまうことがあります。
これは決して「わがまま」ではありません。
感情をコントロールするための発達段階にあるということを、支援者はしっかり理解しておく必要があります。
感情の裏にある「伝えたい気持ち」に気づく視点
行動に現れた感情の裏には、こんな気持ちが隠れているかもしれません:
- 【怒り】…「分かってもらえない」「思い通りにいかない」「悔しい」
- 【悲しみ】…「ひとりぼっち」「認めてもらえない」「うまくできない」
- 【不安】…「先が見えない」「怖い」「失敗したらどうしよう」
- 【喜び】…「伝えたい」「一緒に楽しみたい」「もっと関わりたい」
支援者が「怒っているな」ではなく、**「なぜ怒ったのか」「その奥にはどんな気持ちがあるのか」**を読み取ろうとすることで、対応はぐっと変わります。
感情理解を深める支援の実践ポイント
1. 感情カードや表情イラストを活用する
言葉にするのが難しい子には、「今の気持ちどれかな?」と視覚的に気持ちを表現できるツールが効果的です。
選ぶだけでも自己理解につながり、支援者が気持ちに寄り添うきっかけになります。
2. 感情に名前をつけてあげる
「それは悲しかったね」「悔しかったんだね」など、子どもの代わりに言語化することで、気持ちの整理と落ち着きにつながります。
3. 感情を受け止めてから対応する
「そんなことくらいで怒らないの」「我慢しなさい」ではなく、
「怒る気持ちも分かるよ。その上で、どうしたらよかったかな?」とまず感情を肯定し、次の行動を考えるサポートをします。
感情に巻き込まれない支援者の心の保ち方
感情的な場面が続くと、支援者も心が疲弊してしまいます。
そこで大切なのが、「巻き込まれず、寄り添う」ための工夫です。
- 自分の気持ちも客観的に見つめる(「今、私も焦ってるな」と気づく)
- チームで共有・相談し、支援を一人で抱え込まない
- 「完璧な対応」より「誠実な姿勢」を大切にする
子どもの感情を受け止めるには、支援者自身の感情にも丁寧であることが求められます。
保護者との感情理解を共有する視点
子どもの感情的な行動について、保護者から「すみません」「家でもこうなんです」と申し訳なさそうに言われることもあります。
そのとき、支援者として伝えたいのは、
- 「感情は悪いものではないこと」
- 「支援でコントロールできるよう練習していること」
- 「その子なりに頑張っているという視点」
そして、家庭と連携して“感情との付き合い方”を一緒に育てていくパートナーであることが伝わると、保護者も安心します。
まとめ:感情を「育てる」支援が、信頼を生む

子どもの感情に寄り添う支援は、決して「甘やかす」ことではありません。
「怒ること」「泣くこと」「不安になること」を否定せず、一緒に受け止め、言葉にして、次の行動を考えるプロセスこそが、感情の成長を支える土台です。
支援者の役割は、「落ち着かせること」ではなく、感情を整理する力を育てること。
その積み重ねが、子どもの自信を育み、安心できる関係性をつくっていきます。
感情に振り回される日もあるかもしれません。
でも、今日のあなたのひとことが、きっと誰かの心をあたためています。