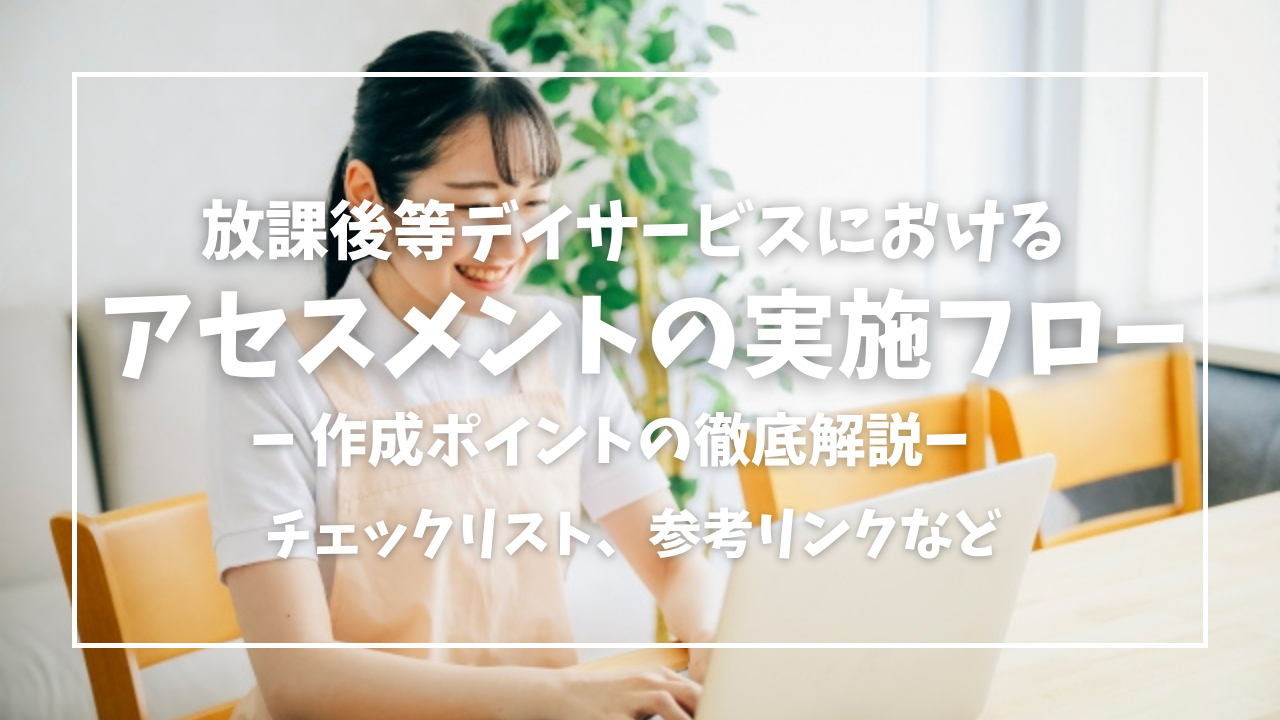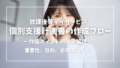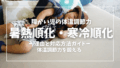🔍 1. はじめに — アセスメントとは何か?その重要性
アセスメントとは、児童の日常生活や発達・行動特性を「評価・分析」し、個別支援計画作成の基盤となる情報を整理するプロセスです。児童福祉法に基づく放課後等デイサービスでは、児発管が実施主体となり、日常観察と聞き取りを通じて「本人と環境」の情報を収集します。
重要なのは、単なる情報集めにとどまらず、課題とニーズを分析し、「支援目標へつなげる」こと 。
📋 2. アセスメントの全体フロー(7ステップ)

- 準備段階:目的と同意取得
- アセスメントの目的を保護者・児童に説明し、同意を得る。
- 実施日、場所、関係者(学校、保護者、他機関)を明確に。
- 情報収集:フェイスシート/既存記録の確認
- 基本情報(生年月日・学校・家族構成・医療歴など)。
- 福祉サービス利用状況や標準調査(5領域20項目)結果の確認。
- 聞き取り(インタビュー)
- 保護者:生活習慣・家庭での困りごと、本人希望など。
- 児童:言葉・行動観察、言語コミュニケーションの方法も活用。
- 観察記録
- デイ利用の様子を記録:「動作」「環境反応」「交流」などを観察。
- 情報整理・分析
- 得意・困難・環境要因を5領域ごとに分類し整理。
- フェイスシートとアセスメントシートの使い分け。
- 課題抽出・目標設定
- 1年後や半年後の姿をイメージし、強みを活かした課題を設定 。
- 報告・共有・次ステップへ
- 保護者・スタッフへ振り返り。個別支援計画原案やモニタリング会議に反映。
🧠 3. 5領域別アセスメントの具体的視点
健康・生活
- 観察:食事・排泄・睡眠習慣、服薬、アレルギーなど 。
運動・感覚
- 運動スキル(バランス、歩行)。感覚への反応や統合的な感覚行動。
認知・行動
- 課題解決、時間理解、注意力などを観察・標準テストの活用も可 。
言語・コミュニケーション
- 発語のレベル、非言語コミュニケーション(ジェスチャー、絵カード)。
人間関係・社会性
- 交流時の順序を待つ、協調行動、社会的ルールの理解。
✨ 4. 実務で使えるツールと資料
- フェイスシート:基本情報を速やかに共有 。
- アセスメントシート/表:5領域20項目の正式フォーマットが市町村から提供。
- 標準化ツール:Vineland‑IIなど、適応行動評価尺度の活用が推奨 。
🔄 5. PDCAサイクルとの連携
アセスメントはPDCAの「Plan」部分であり、モニタリングでCheckされ、必要なら改善(Action)し、再Planされます 。
モニタリング会議には、収集したアセスメント情報をもとに支援効果や課題の検討が不可欠です。
⚠️ 6. 失敗しない!注意点チェックリスト

- 初回・定期アセスメントの同意取得が未実施では実地指導リスク。
- 情報源は多様に:本人・保護者・学校・他機関も含めること。
- 書類の形式や記録の見える化は必須(自治体の様式に合わせる)。
- 強みに目を向ける観点を忘れず、「できる」を伸ばす姿勢が重要 。
✅ 7. まとめ — アセスメントで迷わないためのSTEP
| ステップ | 中心内容 |
|---|---|
| 1. 同意取得 | 目的・流れ・関係者への説明 |
| 2. 情報収集 | フェイスシート、標準調査結果など |
| 3. 聞き取り | 保護者・児童・他機関 |
| 4. 行動観察 | 放デイ利用時の自然場面で |
| 整理・分析 | 5領域・強みと課題の分類 |
| 6. 目標設定 | 長短期で支援目標を明確化 |
| 共有・次へ | 個別支援計画原案へ反映しPDCAへ |
結論:アセスメントは「迷わない支援」の出発点であり、「計画と実践の精度」を高める根幹です。上記のフローとチェックリストを活用することで、質の高い支援づくりが可能になります。
📚 参考リンク・資料ダウンロード
- 市町村提供「5領域20項目調査」資料(こども家庭庁)
- 郡山市公式ウェブサイト 郡山市アセスメントシートPDF
💡 最後に
丁寧なアセスメントは、児童一人ひとりに合わせた支援への第一歩。迷わず取り組むためには、このフローを基盤に実務を積み重ねることが大切です!