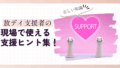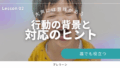プログラムに悩む職員さんへ
放課後等デイサービスの現場でよく聞かれる悩みの一つが、「今日、何の活動をしよう…」というプログラム選び。
毎日違う子どもたちの様子に合わせて、飽きさせず、でも意味のある活動を考えるのは、想像以上に大変なことです。
「ネタが尽きた…」
「このプログラム、子どもたちに合ってる?」
「やってみたけど、いまいち盛り上がらなかった…」
そんな不安や迷いを感じたことがある職員さんに向けて、この記事では今日から使える放デイ向けプログラムの実例と、活動を成功させるヒントをまとめました。
活動そのものも大切ですが、子どもとの関わりの中で「どんな目的で、どんな成長を支えたいのか」という視点を持つことで、プログラムの価値は何倍にも広がります。
「次、これやってみよう!」と思えるような、引き出しを増やすきっかけになれば嬉しいです。
プログラムの選び方の基本:目的とねらいを明確に

プログラムを選ぶとき、ついつい「楽しそう」「盛り上がりそう」といったイメージ先行で決めてしまうことはありませんか?
もちろん、楽しさは大切な要素ですが、支援の現場においては「この活動で何を育てたいのか」という目的とねらいを持つことが何より重要です。
たとえば、みんなで工作をするプログラム。
単に「ものを作る楽しさ」だけでなく、「集中力を養う」「順番を守る」「手先の使い方を学ぶ」といった複数の発達支援の要素が含まれています。
そこに意識を向けることで、同じプログラムでも支援の深さが変わります。
目的を明確にすると、以下のようなメリットがあります:
- 活動の工夫ポイントが見えてくる(どこを強調すべきか)
- 子どもの反応を見たときの評価軸ができる(ただ楽しんだだけでなく、成長の手応えを感じられる)
- 保護者への説明がしやすくなる(どんな力を育てようとしているかを伝えやすい)
「何のためにやるのか?」を常に意識することで、支援者としての視点も育っていきます。
楽しさと発達支援を両立させたプログラム設計こそが、放デイ職員の腕の見せどころです。
1. 感覚統合あそび
感覚統合とは、視覚・聴覚・触覚・前庭感覚(バランス感覚)など、さまざまな感覚を脳で整理・統合し、適切な行動につなげる力のこと。
発達に特性がある子どもは、これらの感覚処理がうまくいかず、日常生活で「落ち着かない」「過敏」「鈍感」といった様子を見せることがあります。
そこで役立つのが、**「感覚統合あそび」**です。
あそび感覚で楽しみながら、自然と感覚を刺激・調整することができるため、子どもたちにも大人気の活動のひとつです。
具体例:
- バランスボールやトランポリン(前庭感覚・体幹の刺激)
- ボールプール(触覚・安心感)
- トンネルくぐりやマット運動(身体の動かし方の感覚を育む)
- 手触りの違う素材で感覚遊び(感覚過敏の軽減)
このような活動は、「落ち着く時間をつくる」「体を動かす機会を設ける」だけでなく、感覚過敏の緩和や、ボディイメージの育成にもつながる支援です。
活動を通じて「気持ちよかった」「またやりたい」と思ってもらえたら、それがもうひとつの成功体験。
楽しく遊びながら、子どもが自分の体と感覚に気づいていくサポートになります。
2. ソーシャルスキルトレーニング(SST)
ソーシャルスキルトレーニング(SST)は、社会生活を送るうえで必要な「人との関わり方」や「場面に応じた行動」を練習するプログラムです。
発達障害のある子どもたちは、暗黙のルールや相手の気持ちを察することが難しいことがあり、友達との関係づくりや集団行動で困りごとを抱えることがあります。
SSTは、そのような子どもたちにとって、人と関わるスキルを“見える化”して学べる貴重な機会になります。
具体例:
- あいさつの練習(目を見て、声の大きさ・タイミングなど)
- 順番・ルールを守る遊び(カードゲーム、ボードゲームなど)
- 気持ちの伝え方ロールプレイ(「いやなときはこう言おう」など)
- 相手の気持ちを想像するワーク(絵カードやマンガを使って)
SSTのポイントは、「正解を押しつけないこと」。
子どもが自分の経験として「こういう時はこうしてみようかな」と思えるように、練習と対話を重ねることが大切です。
また、できたときはしっかり褒めて、「人と関わること=楽しいこと」と感じられるようなポジティブな体験につなげていくと、自然と日常にも活かされていきます。
3. クッキング活動
クッキングは、楽しみながら多くのスキルを育てられる、放デイでも特に人気のプログラムの一つです。
子どもたちにとっては「ごっこ遊び」の延長のように感じられつつ、手先の操作・手順の理解・役割分担・達成感など、さまざまな力が自然と身につきます。
具体例:
- おにぎり作り(ラップを使って握るだけ)
- サンドイッチ(パンに具材を挟む簡単工程)
- フルーツポンチ(果物を切って混ぜる)
- ホットケーキ(焼く工程までを体験)
クッキング活動のメリットは、「生活スキル」の習得にもつながること。
料理をすることで、「自分でできた!」という自己効力感が育まれます。
また、協力して作るプロセスの中には、順番を待つ・人と協力する・感謝するといった社会性を学ぶチャンスも豊富です。
注意点としては、衛生面やアレルギーの配慮、安全対策(包丁・火など)を必ず行うこと。
役割をあらかじめ分けたり、見通しを持てるように工程を視覚化するなどの工夫で、どの子も安心して参加できる環境を整えましょう。
4. ビジョントレーニング
「見る力=視覚機能」は、学習や運動、日常生活のあらゆる場面で必要なスキルです。
特に発達に特性のある子どもは、視線の動かし方や注視、目と手の協応に苦手さを抱えていることが多く、「文字が読みにくい」「黒板の内容がノートに写せない」などの困り感につながっていることがあります。
そんな“見えにくさ”を補うための支援が、ビジョントレーニングです。
具体例:
- まねっこ体操(指先や視線を使って真似する動き)
- 目で追う練習(ビー玉を転がして追う、レーザーポインターを追うなど)
- 迷路や点つなぎ(視線のコントロールと集中力の練習)
- タングラムや積み木パズル(空間認知や手先の協応)
ポイントは、「トレーニング」というよりは**“あそび”の中に自然に取り入れること**。
視覚機能を伸ばすという意識は持ちつつ、子どもが「楽しい!」と思える工夫を凝らすことで、繰り返し取り組みやすくなります。
成果がすぐに見える支援ではありませんが、コツコツと積み重ねることで「見る力」が少しずつ育ち、学習や生活へのストレスが軽減される効果が期待できます。
5. 自己表現プログラム(お絵かき・工作など)
言葉では気持ちをうまく伝えられない子どもたちにとって、**絵や工作といった「表現活動」は、心の内側を外に出す大切な手段です。
自己表現のプログラムは、自由な発想と創造性を伸ばすだけでなく、「自分の思いを人に伝える」「達成感を得る」**といった体験にもつながります。
具体例:
- お絵かき自由帳(テーマを決めず、好きに描いてOK)
- 季節の工作(こいのぼり、クリスマス飾りなど)
- コラージュアート(雑誌や色紙を使って好きな世界を表現)
- 感情を絵で表すワーク(「うれしい」「悲しい」を色や形で)
このような活動では、「上手に描けたか」ではなく、「何を描いたか」「どう感じたか」を大切にする姿勢が必要です。
評価よりも共感。「へぇ、それは面白いね!」「どんな気持ちだったの?」と、作品を通して対話することで、自己理解や感情の整理にもつながります。
また、作品を飾ったり、持ち帰ってもらうことで「自分が認められた」という実感を持つことができ、自己肯定感の向上にも効果的です。
雨の日・スペースが限られている日にも使える!室内プログラム例

放デイでは、「今日は雨だから外で遊べない」「スペースが狭くて体を動かす活動が難しい」――そんな日も少なくありません。
でも大丈夫。限られた環境でも、子どもたちが楽しみながら成長できるプログラムはたくさんあります。
室内でもできるおすすめプログラム:
1. タオル綱引き
スペース不要で体幹を使える運動遊び。2人1組でタオルを引っ張り合うことで、筋力やバランス感覚を養えます。
2. お手玉・紙コップタワー
手先を使う遊びは集中力や巧緻性の支援に最適。ゲーム形式にすると盛り上がります。
3. 室内SSTゲーム
「○×クイズ」「感情カード当てゲーム」「いいとこ探しビンゴ」など、遊びながらコミュニケーションスキルを育てるアクティビティ。
4. サーキット風活動(小規模)
イスの周りを歩く→お手玉を乗せる→パズル1個解く、などの小ステーション形式。順番や待つ力を育てる効果も。
5. リラックスタイム(音楽・読み聞かせ)
刺激が多い日こそ、静かな活動で心を整える時間も大切に。安心できるルーティンとしても効果的です。
室内活動のポイントは、「制限の中でも“できること”を見つける視点」。
子どもたちは、大人の工夫次第でどんな環境でも楽しめる力を持っています。
支援者の発想が、活動の質を左右するカギになるのです。
「ちょっとした時間」に便利な短時間アクティビティ
活動と活動の合間、帰りの時間までの少しの空き時間――
放デイでは、5分~10分の「すきま時間」をどう活用するかが支援の質を左右することもあります。
そんなときに役立つのが、短時間でできて、リズムを整えるアクティビティです。飽きずに楽しめて、切り替えにもぴったりなプチプログラムをご紹介します。
おすすめ短時間アクティビティ:
1. まねっこじゃんけん
普通のじゃんけんに、「声のトーン」「動き」「表情」などをアレンジ。観察力と注意力も育ちます。
2. 色指示ゲーム(例:「赤いものを3つ探そう」)
空間認識や色の識別、記憶の力を使うシンプルゲーム。室内で手軽にできます。
3. 感情カードを1枚引いて「最近こんな気持ちあった?」
自己理解・自己表現の支援になるミニSST。
4. なぞなぞ・しりとり・早口言葉
言語的なやりとりを楽しむ知的遊び。子ども同士の関わりも促します。
5. 呼吸エクササイズ(3秒吸って、3秒止めて、3秒吐く)
テンションが高いときや帰る前の落ち着きタイムに効果的。
このような活動は、「ただの暇つぶし」ではありません。
子どもが無理なく楽しめて、次の行動へのスムーズな切り替えができる工夫が詰まっています。
何気ない時間こそ、支援のチャンス。
ちょっとしたアクティビティの引き出しが多い職員さんほど、現場での安心感は増していきます。
プログラムを成功させるためのポイント3つ
どんなに素晴らしいプログラムでも、「うまくいかない…」「子どもが乗ってこない…」ということはあります。
そこで重要なのが、“内容”よりも“運び方”や“関わり方”。プログラムを成功に導くための、支援者が押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
1. 「見通し」を持たせる
子どもたちは「何をするのか分からない」と不安になりやすいものです。
始める前に「今から〇〇をします」「終わったら△△に移ります」と伝えるだけで、安心感と集中力がアップします。
視覚スケジュールやイラストの活用もおすすめです。
2. 「ちょっとできた!」を拾う
活動中の小さな成功を見逃さず、「そこまでできたね!」「さっきより早くできた!」と声をかけることで、子どもは自信を持ち、意欲的に参加できるようになります。
うまくいかない部分ではなく、「できた部分」にフォーカスすることがカギです。
3. 柔軟に“切り替え”る準備を
どんなに準備しても、子どもが全員同じように集中できるとは限りません。
そんな時は、「無理にやらせない」「内容や方法を切り替える」柔軟さが大切です。
「やらない選択肢」もOKとすることで、子どもの尊重と安心感につながります。
プログラムは、あくまで“支援のための手段”。
内容そのものよりも、「どう進めるか」「どう関わるか」で、子どもたちの体験はまったく変わります。
子どもの反応を見ながら“変化”を楽しむ支援

放デイでの支援は、計画通りにいくとは限りません。
プログラムを立てても、「今日は集中できない子が多い」「やる気が見えない」「一部の子だけが参加している」――そんな場面は日常茶飯事です。
でも、それは失敗ではありません。
大切なのは、「反応をどう受け取り、どう応じるか」です。
たとえば、誰も興味を示さなかった活動を、「じゃあ今日はこうしてみようか!」と少し形を変えてみたら、一気に場が盛り上がることがあります。
あるいは、子どもの一言から、全く違う活動にスイッチしたことで、思いがけず良い効果が生まれることも。
支援者として必要なのは、「子どもは生き物であり、毎日違っていい」という柔らかい視点です。
“変化を楽しむ”マインドが支援を豊かにする
- 「うまくいかなかった理由」より、「次どうすれば楽しめるか」を考える
- 子どもの表情や反応に敏感になる
- 職員同士で状況をシェアし、連携して対応する
予定にしばられすぎず、「今、この子たちにとってベストなことは何か?」を常に問いながら動ける柔軟さ。
それが、放デイ職員にとっての“プロの感覚”です。
変化を恐れず、子どもたちと一緒に笑いながら、日々の支援を“つくっていく”。
それこそが、放デイならではの楽しさであり、魅力ではないでしょうか。
まとめ
放課後等デイサービスのプログラムは、単なる「お楽しみ」ではなく、子どもの成長を支える大切な支援の一部です。
今回ご紹介したように、感覚統合あそびやSST、クッキング、短時間アクティビティまで、多種多様なプログラムには、それぞれに目的と意味があります。
大切なのは、活動の内容よりも、その子に合った関わり方を意識すること。
「何を育てたいか」を軸にしながら、目の前の子どもたちの反応を丁寧に読み取り、柔軟に対応する姿勢が、支援の質を高めます。
ネタ切れや不安に悩む日もあるかもしれません。
でも、あなたの「よくしたい」「楽しませたい」という思いは、子どもたちにちゃんと伝わっています。
この記事が、明日の活動のヒントになれば嬉しいです。
CTA(行動喚起)
「今日、これやってみようかな」と思えるものがあれば、ぜひ現場で実践してみてください。
小さな「楽しい」「できた」の積み重ねが、子どもたちの自信と笑顔を育てていきます。
記事の感想や、現場でのエピソードもぜひコメントで教えてくださいね。
あなたの実践が、誰かの支援のヒントになるかもしれません。