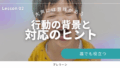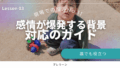「えっ、支援で“無視”なんてあり得るの…?」
そんな驚きや戸惑いの声を、支援の現場で耳にすることがあります。
実はこれ、「計画的無視(Planned Ignoring)」という、行動療法に基づいたれっきとした支援技法なんです。
この記事では、誤解されやすいこのアプローチについて、支援者・保護者の両視点から解説します。
無視するのは“子ども”ではなく“行動”
 「無視」と聞くと、冷たい、ひどい、子どもが可哀想…そんな印象を持つ方が多いのではないでしょうか。
「無視」と聞くと、冷たい、ひどい、子どもが可哀想…そんな印象を持つ方が多いのではないでしょうか。
ですが、ここでいう“計画的無視”とは、子どもの行動の一部に対して、あえて反応しないという方法です。
たとえば――
- わざと大声を出して注意を引こうとする
- 授業中に机を叩く
- 先生を困らせることでかまってもらおうとする
こうした“注目を集めるための行動”に対して、支援者が反応しないことで、
「このやり方では注目されないんだな」と子どもが気づき、その行動を減らしていくのが目的です。
なぜ“反応しない”ことが効果的なの?
人は、誰かに注目されることで行動が強化されます。
子どもも同じで、叱られることでさえ「かまってもらえた」と感じて、繰り返してしまうことがあります。
あえて反応しないことで、「効果がない」と子どもが学ぶ。
そして、静かにできたときや落ち着いて行動できたときに注目することで、良い行動が増えていくんです。
ただし、無視すればいいわけじゃない
この技法には注意点もあります。万能ではなく、正しく使わなければ逆効果になることも。
子どもによっては不安が強くなることもある
自閉スペクトラム症など、周囲の反応に敏感な子は「無視された」と感じて不安を強める可能性があります。
一時的に行動が悪化する「バースト」も
最初は行動が激しくなることもありますが、ここでぶれてしまうと「強くすれば注目される」と学習させてしまいます。
感情や存在を否定することではない
あくまで「特定の行動」に反応しないだけ。
普段の関わりでしっかり愛着と信頼を築くことが大切です。
保護者の皆さんへ:こんなときは遠慮なく聞いてください
 もし支援者が「無視しているように見える対応」をしていたら、
もし支援者が「無視しているように見える対応」をしていたら、
「なぜその対応なのか?」「子どもはどう感じているか?」を遠慮なく聞いてください。
計画的無視は、支援者だけでなく保護者との信頼関係があってこそ意味のある手法です。
納得しながら一緒に取り組むことが、子どもにとっても一番の支えになります。
まとめ:冷たく見えて、実はあたたかい支援
「計画的無視」は、子どもの成長を本気で願うからこそ使われる支援技法のひとつ。
ただ叱るのではなく、良い行動を伸ばすための、前向きなアプローチです。
冷たく見えるかもしれませんが、その奥にあるのは本気の支援と愛情。
ぜひ、その意図に目を向けてみてください。
子どもたちが、自分らしく成長していけるためのヒントになりますように。