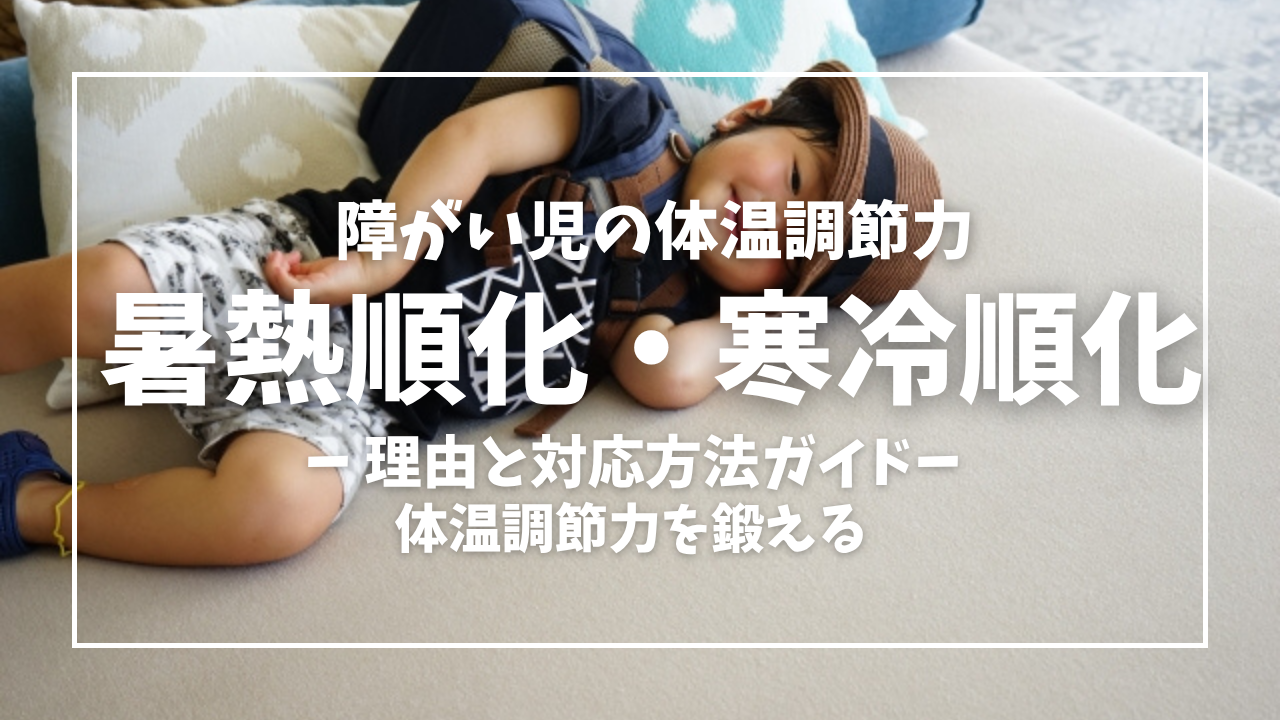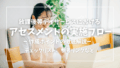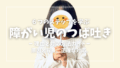1. はじめに:体温調節が未熟な障がい児への配慮
障がいのある子どもは、感覚過敏や自律神経の調整機能に偏りがあるため、暑さ(夏バテ)や寒さ(冬バテ)に対する順応性が一般児より低い傾向があります。
実際、子どもは成人より体温調節機能が未熟で、発汗や皮膚血流に頼って体温をコントロールしていますが、障がい児ではさらに個人差が大きく、中でも暑熱・寒冷への順化には配慮が必要です。
2. 暑熱順化とは?メカニズムと効果

暑熱順化とは、高温環境に少しずつ身体を慣らし、発汗量・皮膚血流・心拍数などの調整能力を向上させる過程です。
多くの場合、10~14日間の適度な暑熱曝露で効果が得られるとされ、体温の急上昇を防ぎ、熱中症リスクの低減につながります。
特に、東京五輪などで報告のあるパラアスリートにおいて、発汗量・体内水分量の改善が確認された研究もあり、障がい児にも応用の可能性があります。
3. 寒冷順化とは?対応力を高めるメリット
寒冷順化は、低温に身体を慣らすことで代謝量の上昇・皮膚血流の調整・保温行動の促進につながります。
動物実験により、視床下部での体温感受性適応、ヒトでは低温環境下での生理反応の安定化が報告されており、寒冷環境下での健康維持に効果があるとされています。
4. 障がい児における順化の特徴と注意点
- 感覚過敏がある場合:暑熱順化では着衣・冷房調整に敏感な児がいるため、衣服の素材・脱ぎ着のしやすさを工夫。
- 自律神経発達の偏り:重度の脳性麻痺などでは発汗が不十分となるケースあり。効果に個人差がある点に注意が必要。
- コミュニケーション困難:暑熱や寒冷による体調不良を適切に訴えられないケースが多く、観察と記録が不可欠です。
5. 放デイ現場での実践ステップ
ステップ①:アセスメント
既往症や体調・支援歴をチェックし、個別順化プランを立案。
ステップ②:計画的曝露
暑熱順化では10~14日間の運動・ボディワークを高温環境下で実施。
寒冷順化は涼しい環境で軽運動やクールダウン活動を数週間行います。
ステップ③:モニタリング
体温、脈拍、発汗量、主観的不快感を記録し進捗を把握。
ステップ④:段階調整と安定化
暑熱順化後は通常環境・登下校シミュレーションで耐熱性を継続。寒冷順化後は冬場の活動プランに反映。
ステップ⑤:家族と共有
家庭でも暑熱・寒冷環境への曝露を継続できるよう理解と協力を促す。
6. 生活習慣と支援プログラムの工夫
- 水分補給習慣の促進:こまめな声かけや冷水・スポーツドリンクを定期提供。
- 衣類・冷房調整:吸汗速乾素材の使用、暑い日は冷房28°C設定など環境配慮。
- 保護者向け情報提供:UNICEFや厚労省の熱中症予防ガイドを共有し家庭との連携を強化 。
- 福祉機器活用:温度センサー付き服、体温モニターなどの導入も検討。
7. ケーススタディ&成功のコツ
Aさん(小学生・脳性麻痺)
初期に38.5℃の発汗不良が見られたが、12日間の段階的暑熱順化で発汗反応が現れ、重度の熱ストレスが緩和された。
Bさん(中学生・自閉症)
冬の屋外活動で震えや拒否行動が頻発。寒冷順化を計画し3週間後には外遊びへの抵抗が改善され、保護者からも好評を得た。
8. 専門家の声と今後の展望
長崎大学などでは、視床下部の温度感受性に関する動物・ヒト研究を通じ、暑熱・寒冷順化の中枢的メカニズムの解明が進展しています。
一方で、スポーツ分野ではパラアスリートによる順化の研究が報告されており、障がいがある子どもへの応用が今後拡大する見通しです。
・・・
以上を踏まえると、放課後等デイサービスでは単に順化だけでなく、体調記録・生活習慣改善・環境設計を組み合わせた支援が効果的です。
✅ まとめと提言

- 暑熱・寒冷順化は障がい児の体温調節支援に有効だが、個別ケアと観察が前提です。
- 運動・環境・水分・衣類・家庭連携が五本柱。
- アセスメント・計画・記録・振り返り・共有のPDCAサイクルが支援の質を守ります。
📣 まずは1週間の「暑熱順化プラン」を試し、体調変化を記録・分析することから始めてみましょう。それが支援の安心と成長につながります。
参考サイト KAKEN・熱中症ゼロへ – 日本気象協会推進