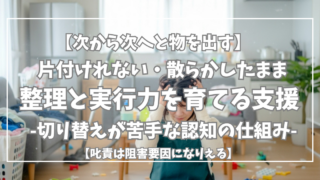 支援
支援 片付けない・散らかしたままの子どもへの支援法──放デイで育てる整理・実行力
1. はじめに:片付けない・汚したまま…なぜ目立つのか放課後等デイサービスでは、子どもたちが遊んだ後や活動後に 物を片付けない・使った場所を汚したままにする 行動が目立つことがあります。大人目線では「片付けなさい」と叱ってしまいがちですが、...
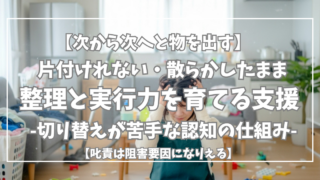 支援
支援 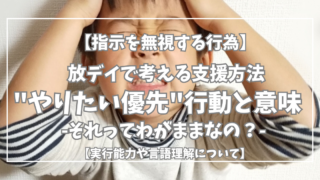 支援
支援 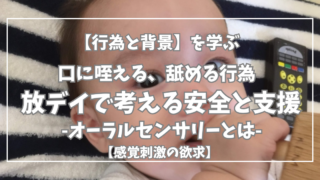 支援
支援 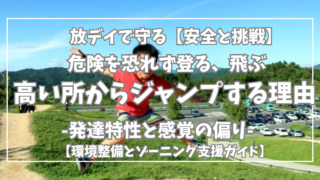 支援
支援 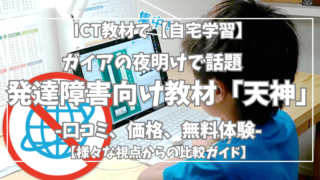 PR
PR 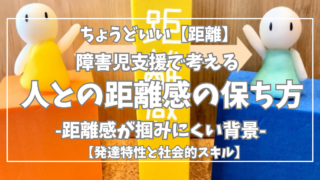 支援
支援 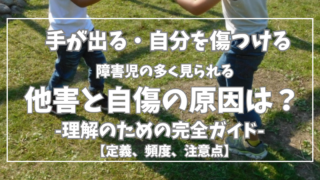 支援
支援 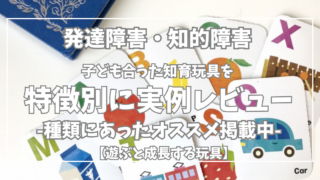 PR
PR 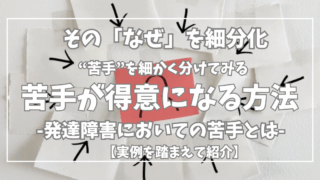 支援
支援 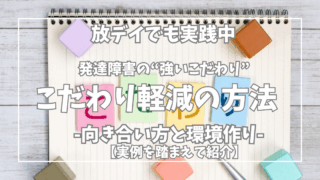 支援
支援