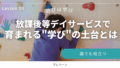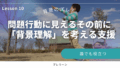はじめに:「どうしてそんな言い方するの?」と悩んだら
放課後等デイサービスや家庭での関わりの中で、「急に怒鳴り出す」「泣くしかできない」「言いたいことが伝えられない」といった子どもの姿に戸惑うことはありませんか?
感情表現の難しさは、発達特性のある子どもたちによく見られる課題です。
でも、それは**「気持ちがない」わけでも「伝える気がない」わけでもない**のです。
うまく表現する“方法”や“きっかけ”を、まだ十分に学べていないだけ。
この記事では、ご家庭で無理なくできる感情表現の練習方法と、放デイ支援者との連携のコツをご紹介します。
感情表現が苦手な子が感じていること

感情表現が苦手な子どもは、こんなことを感じているかもしれません:
- 「言いたいけど、うまく言葉にならない」
- 「何が嫌なのか自分でもよく分からない」
- 「伝えてもわかってもらえなかった経験がある」
- 「気持ちを言うより、黙っていたほうがラクだ」
こうした経験が積み重なると、「どうせ分かってもらえない」「言っても意味がない」と思い込むようになり、
感情を外に出す力がどんどん弱くなってしまいます。
家庭でできる!感情表現を育てる5つの練習法
1. ■ 「気持ちカード」で遊ぶ
- 喜び・怒り・悲しみ・不安などをイラストで表現したカードを使い、「今の気持ちはどれ?」と日常的に確認
- 言葉が苦手でも、指差しやジェスチャーで気持ちを伝えられるように
2. ■ 絵本やアニメのキャラクターで気持ちを考える
- 「この子、どんな気持ちかな?」「どうして怒ったんだと思う?」と他者の気持ちを想像する練習に
- 実際の感情を客観的に捉える力が養われます
3. ■ “おうちルール”で感情の名前を教える
- 例:「怒ってもいいけど、モノは投げない」「悲しい時は教えてね」
- 感情を否定せず、「どう伝えるか」を練習するチャンスに
4. ■ 親も感情を言葉にしてモデルになる
- 「ママ、今日は疲れてイライラしちゃった」
- 親の感情表現を見せることで、「気持ちを言葉にするってこういうことなんだ」と理解が深まります
5. ■ 成功したらしっかり褒める
- 「今、ちゃんと“イヤ”って言えたね!」「悲しいって教えてくれてありがとう」
- 気持ちを出せたこと自体を価値ある行動として承認してあげましょう
放デイとの連携で家庭支援がもっとラクに
家庭での練習は、放デイでの支援とつながることでさらに効果が高まります。
- 「家でこんなことがありました」と放デイに伝える
- 放デイで使っている感情カードや表現方法を家庭でも活用
- 「最近、“嬉しい”ってよく言ってます」と、家庭の様子を共有
支援者と保護者が同じ方向を向いて関わることで、子どもは「どこでも同じように安心して気持ちを伝えていいんだ」と感じられるようになります。
感情表現の練習で気をつけたいポイント
- 無理に言わせない:「何が嫌なの!?」と問い詰めるのは逆効果
- まずは“受け止める”:言葉にならないときは「つらかったんだね」と代弁を
- 気持ちを否定しない:「泣くのはやめて」ではなく、「泣きたくなるくらい悲しかったんだね」
大切なのは、“言えた内容”より“言おうとしたこと”に目を向けること。
そこに気づけるかどうかが、支援の質を左右します。
まとめ:「言えた!」が自己肯定感を育てる

子どもが自分の気持ちを表現できるようになることは、安心・自信・人とのつながりを育てる第一歩です。
家庭でも無理なく、楽しみながらできる工夫はたくさんあります。
今日から始められる小さな練習を、焦らず、温かく見守りながら続けていきましょう。
放デイと家庭が手を取り合って取り組むことで、子どもたちは少しずつ、「伝えるって気持ちいい」と思えるようになっていきます。