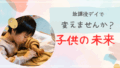なぜ「支援の仕方」に迷うのか?
放課後等デイサービス、通称「放デイ」で働く中で、ふと立ち止まる瞬間があります。
「これって、本当に子どものためになってるのかな?」
「もっと良い支援の方法があるんじゃないか…」
そんな悩みを抱える職員さんは、あなただけではありません。
支援とは、正解のない試行錯誤の連続です。目の前の子ども一人ひとりに違った背景と特性がある以上、「こうすれば完璧!」なんて方法は存在しません。だからこそ、自信を持てずにモヤモヤしてしまうのも自然なことです。
でも、ちょっとした視点の切り替えや関わり方の工夫で、支援は大きく変わります。
本記事では、放デイで働く職員さんが「正しい支援って何だろう?」と迷ったときに立ち返れるヒントを、具体例を交えてお届けします。あなたの支援が、きっと子どもの未来を照らしますように。
放デイ職員の役割とは?「支援者」であるということ

放課後等デイサービスの職員として働いていると、つい「お世話係」や「安全管理の担当者」のような立ち位置にとどまってしまいがちです。もちろん、子どもの安全を守ることは大前提。でもそれだけで終わってしまっては、支援の本質を見失ってしまいます。
私たち放デイ職員の役割は、「子ども一人ひとりが、その子らしく育ち、社会とつながる力を育むことを支える存在」であることです。つまり、**単なる見守りではなく、発達や生活スキルの成長を後押しする“支援者”であるという視点が求められます。
支援者とは、子どもに「何かをさせる人」ではなく、「どうすればできるか」を一緒に考え、寄り添う存在です。「できないから手を貸す」のではなく、「できる力を育てるために環境を整える」のが支援者の仕事。
子どもとの関係性の中で、「あの先生といると安心する」「自分のことをちゃんと見てくれている」と感じてもらえること。それが信頼の土台となり、支援の効果を何倍にも高めてくれます。
このパートで一番伝えたいのは、「あなたがどう関わるかで、子どもの未来が変わる可能性がある」ということ。支援者としての意識を少し高めるだけで、日々の関わりは確実に変わっていきます。
子ども理解の第一歩:発達特性を知る
支援を始めるうえで、最初に意識したいのは「子どもをよく知ること」です。
その中でも特に大切なのが、発達特性を理解する視点です。
放デイを利用する子どもたちは、多くの場合、発達に何らかの特性を持っています。注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)など、その内容や程度は本当にさまざま。でも、私たちが知っておきたいのは「診断名」そのものよりも、それぞれの子がどんなことで困りやすいのか、どんな支援で安心できるのかという具体的な視点です。
たとえば、ASD傾向のある子は「予定が変わるとパニックになる」ことがあります。この子にとっては、「今から何をするのか」がわからないだけで、強い不安につながってしまうのです。そんなときは、「予定を視覚で伝える」「繰り返し予告する」など、見通しを持たせる支援が有効です。
また、ADHDの子どもは、「じっとしていること」や「指示を一度で聞いて行動すること」が苦手だったりします。でも、それは「わがまま」でも「聞いていない」わけでもなく、脳の働きの特性として、衝動的に動いてしまったり、注意がそれやすいというだけなのです。
このように、子どもが見せる行動には必ず背景があります。支援のスタートは、「この子はなぜこういう行動をとるのか?」という視点で、行動の裏側にある理由を探ること。決して、「問題行動をなくすこと」だけが目的ではありません。
子どもの「困り感」に目を向け、そこに共感を持って接すること。これこそが、支援の第一歩であり、最も重要な土台なのです。
支援の原則:「できない」ではなく「どうしたらできるか」を考える
支援の現場では、子どもたちの「できない」に直面する場面が多々あります。
「指示が通らない」「ルールが守れない」「集中が続かない」──。そんなとき、つい「どうしてできないの?」と感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、その考え方を少しだけ変えてみましょう。
子どもが「できない」のではなく、「今は、できるための環境や手段が整っていない」だけかもしれません。
そう考えるだけで、私たちの支援の視点はぐっと前向きなものに変わります。
たとえば、「お片付けができない」子に対して、叱るのではなく「どこに片付ければいいのかをわかりやすく示す」工夫を加えたとしたら?
「集中できない」子には、「活動時間を短く区切ってこまめに休憩を入れる」工夫が有効かもしれません。
これはつまり、子どもの行動の責任を“本人”だけに押しつけない支援です。
支援者である私たちが、「この子がもっとやりやすくなる方法はないかな?」と常に問い続けることで、子どもは少しずつ「できる体験」を重ねていくのです。
「できない=だめ」ではなく、「できるようになる道筋を一緒に探す」。
それが、放デイにおける本来の“支援”という姿勢であり、子どもの自己肯定感を育む最大の鍵になります。
現場で使える!具体的な支援アプローチ5選

1. 声かけの工夫
子どもへの「声かけ」は、支援の中でも最も頻繁に使われる手段の一つです。
しかし、同じ言葉でも、伝え方やタイミングによって伝わり方は大きく異なります。特に発達に特性のある子どもたちは、曖昧な表現や長い説明を理解するのが難しい場合があります。
たとえば、「ちゃんとして!」という一言。大人にとっては「姿勢を正して、静かにしようね」という意味かもしれませんが、子どもには「何をどうすればいいのか」が分かりづらいのです。結果として、行動につながらないばかりか、指示されたことへの苦手意識を持ってしまうことも。
そこで意識したいのが、具体的でシンプルな声かけです。
「イスに深く座ろうね」「お話はあとにしよう」「手はおひざで待とう」といったように、行動レベルでの指示を心がけると、子どもは自分のすべきことを理解しやすくなります。
また、声のトーンも重要です。高圧的にならないよう、落ち着いたトーンで語りかけることで、子どもは安心して話を聞けるようになります。
「できたね!」と小さな成功を見つけて肯定する声かけも、子どものやる気を引き出す大切なスキルです。
声かけ一つで、子どもの行動が変わる。
そのことを忘れずに、日々の関わりの中で磨いていきたいポイントです。
2. 視覚支援の導入
言葉の説明だけでは理解が難しい子どもにとって、視覚的な情報は大きな助けになります。これが、いわゆる「視覚支援」と呼ばれる支援方法です。
たとえば、活動のスケジュールを文字だけで伝えても、内容が頭の中で整理できず、不安になってしまう子どもも少なくありません。そんなとき、**「今なにをするのか」「次はなにをするのか」**を絵カードやホワイトボードで示すことで、見通しを持てるようになります。
視覚支援にはさまざまな形があります:
- スケジュールボード(1日の流れをイラストで表示)
- 行動カード(やることを1つずつ示す)
- 絵入りのルール表(「順番を守る」「大声を出さない」などを視覚化)
- 感情カード(気持ちを表現するのが難しい子に)
こうした視覚ツールは、「何をすればいいのか」が曖昧だと混乱してしまう子どもにとって、まさに“安心の地図”のような存在です。
また、視覚支援は大人の口頭指示を減らすことにもつながります。その結果、子どもとの関係性がよりポジティブになり、支援そのものがスムーズに進みやすくなるという利点もあります。
「見てわかる」という安心感。
それを提供できるのが、視覚支援の大きな魅力です。
3. 小さな成功体験の積み重ね
放デイの支援において、子どもたちの「できた!」という感覚は、成長を後押しする大きな原動力になります。
しかし、「何かを完璧にやりきる」ことが成功体験だと思い込んでしまうと、支援はどこか苦しいものになりかねません。
大切なのは、ほんの小さな「できた」を拾い上げていく姿勢です。
たとえば、いつも落ち着きがない子が「今日は座ってお話を聞けた」だけでも、それは立派な一歩です。
毎回おもちゃを投げていた子が、「今日は最後まで投げなかった」だけでも、前進と捉えてよいのです。
こうした小さな変化を見逃さず、本人に「できたね!」と伝えることで、自己肯定感がじわじわと育まれていきます。
そしてこの「自分にもできることがある」という実感が、次の行動へのモチベーションを生むのです。
支援者として心がけたいのは、基準を「一般的なできるかどうか」ではなく、「その子の昨日と比べてどうか」で考えること。
周囲と比べず、その子自身のペースでの成長に焦点を当てることで、子どもとの信頼関係も深まり、支援がより効果的になります。
小さな一歩が、未来の大きな一歩になる。
その道を一緒に歩んでいくのが、放デイ職員の大切な役割です。
4. 感情コントロールの支援
放デイの現場では、怒りや不安、混乱といった感情が表に出やすい子どもに接する機会が多くあります。
「急に癇癪を起こした」「気持ちの切り替えができず活動に入れない」──そんな姿を見て戸惑ったことがある職員さんも多いのではないでしょうか。
でも、感情が爆発するのは、「自分でもどうしたらいいのか分からない」から。
そして、それをうまく言葉で伝える力が未発達だからです。
だからこそ、支援者がまず意識したいのは、「感情をコントロールする力は“育てるもの”」という視点です。
たとえば、感情カードやイラストを使って「今の気持ち」を表現する練習をしたり、クールダウンスペースを設けて「気持ちを落ち着かせる」時間を作ることも有効です。
また、「怒ってもいいけど、どうやって表現するかが大事だよ」という**“怒りを否定しない”伝え方**も、子どもの心に安心をもたらします。
もう一つ大切なのは、日頃からの関係性作りです。
安心できる大人がそばにいるという信頼があるだけで、子どもは自分の感情と向き合いやすくなります。
感情は、ダメなものではなく、“大事なサイン”。
そのサインをどう読み取り、どう支えていくかが、職員の腕の見せどころなのです。
5. 保護者との連携
放デイでの支援をより効果的なものにするために欠かせないのが、保護者との連携です。
家庭と放デイ、それぞれでの子どもの様子を共有し、支援の方向性を一致させることで、子どもにとっての“安心できる一貫性”が生まれます。
まず大切なのは、「日々のやり取り」を丁寧に積み重ねることです。
送迎時のちょっとした会話、連絡帳でのやり取りなど、日常的な接点の中で「小さな変化」や「頑張り」を伝えることで、保護者の安心感につながります。
また、支援の方向性について話す際には、専門用語を使わず、分かりやすく伝えることを心がけましょう。
たとえば「社会性が低い」ではなく「お友だちとの関わりにちょっと苦手さがある」といったように、親しみやすい言葉を使うことが大切です。
時には、家庭での悩みや不安を聞く場面もあるかもしれません。
そんなときは「支援者としての立場」だけでなく、「同じ子どもを大切に思う存在」として、共に考え、寄り添う姿勢を見せることで、信頼関係はぐっと深まります。
保護者もまた、「子どもの成長を願い、試行錯誤している支援者」です。
その思いに共感し、伴走する気持ちを持って接することが、より良い支援へとつながっていくのです。
よくあるNG支援とその改善方法

支援の現場では、良かれと思ってやっていたことが、実は子どもにとっては負担になっていた…ということも少なくありません。
ここでは、放デイ職員がやってしまいがちなNG支援例と、その改善ポイントを紹介します。
NG例1:「なんでできないの?」と責める声かけ
→ 改善:「どこが難しかったかな?一緒にやってみようか」と共感をベースに声をかける。
→ 理解されていないと感じると、子どもは心を閉ざします。まずは気持ちに寄り添い、前向きな関わりを。
NG例2:無理に集団に参加させる
→ 改善:「一人でやりたい気持ちがあるんだね。できる範囲で一緒にやってみよう」と本人のペースを尊重。
→ 子どもによっては、人と関わること自体が強いストレスになることも。少しずつ、安心できる場を広げていくのが大切です。
NG例3:「いい子でいようね」と過剰な我慢を求める
→ 改善:「嫌なときはどうしたらいいか、練習しようね」と感情の扱い方を教える。
→ 我慢=良い子、ではありません。感情を抑え込むのではなく、表現と対応の方法を伝える支援が必要です。
NG例4:その場しのぎのご褒美で行動をコントロール
→ 改善:「できた理由」や「自分の頑張り」に気づかせて、内発的動機づけへと導く。
→ ご褒美は一時的な効果しかありません。行動の意味づけを大切にすることで、持続的な成長につながります。
NG支援は、決して「悪意」から生まれるものではありません。
多くは、「知らなかった」や「他に方法が分からなかった」ことが原因です。
だからこそ、日々の関わりの中で「これって本当に子どものためになっているかな?」と自問し続ける姿勢が、より良い支援への第一歩となります。
経験ゼロでも安心!成長する職員の共通点
「福祉の経験がないから不安…」「資格もないし、自分にできるのかな?」
放デイで働き始めたばかりの職員さんから、そんな声をよく耳にします。
でも、安心してください。実は、**支援のスキルよりも先に必要なのは、「姿勢」や「心構え」**なのです。
ここでは、経験ゼロからでも着実に成長していく職員さんに共通するポイントをご紹介します。
1. 子どもへのまなざしが温かい
どんなに支援技術があっても、「この子のことを大切に思っている」という気持ちが伝わらなければ、信頼関係は築けません。逆に、技術が未熟でも「この先生は自分の味方」と思ってもらえれば、子どもは安心して心を開いてくれます。
2. わからないことを「そのままにしない」
「なぜこの行動が起きたんだろう?」「他にいい方法はないかな?」と、自分なりに調べたり、先輩に相談する姿勢が成長につながります。
素直に「教えてください」と言えることは、支援者としての大きな強みです。
3. ミスを恐れず、振り返る力がある
どんなベテランでも失敗はあります。大切なのは、うまくいかなかったときに「なぜそうなったのか」を振り返り、次に活かすこと。「反省=ダメだった」ではなく、「改善のチャンス」ととらえる視点が大切です。
4. チームの一員として関わろうとする
子どもへの支援は、一人で完結するものではありません。職員同士で声をかけ合い、情報を共有しながら「チーム支援」を意識することで、自分も成長し、より良い支援が生まれます。
経験は、あとから必ずついてきます。
最初から完璧を目指さなくても、日々の積み重ねの中で「できること」が確実に増えていくはずです。
「子どもと、しっかり向き合いたい」。
その気持ちこそが、あなたを“信頼される支援者”へと導いてくれます。
まとめ
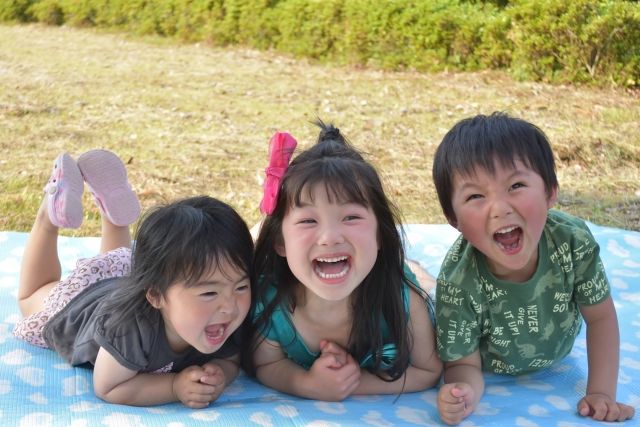
放課後等デイサービスの現場では、子ども一人ひとりの個性や課題に日々向き合いながら、支援者としての在り方を模索している職員さんがたくさんいます。
今回ご紹介したように、「できない」を責めるのではなく、「どうすればできるか」を一緒に考え、支援の質を高める工夫は、現場にすぐ取り入れられるものばかりです。
子どもたちの発達特性を理解し、小さな「できた!」を積み重ね、感情と向き合う力を育て、そして家庭と連携する──。
そのすべてが、子どもたちの未来を広げる支援につながっていきます。
そして何よりも大切なのは、「あなた自身の思いや姿勢」です。
経験の有無にかかわらず、真剣に向き合う心があれば、必ず子どもは応えてくれます。
CTA
もし今、支援に迷いや不安を感じているなら、それは「もっと良くしたい」と思っている証拠です。
どうか、自分を責めず、一歩ずつでも学び続けてください。
この記事が、あなたの支援に少しでも力を添えられたなら嬉しいです。
ぜひ現場で実践してみて、「こんなふうに変わったよ!」という声があれば、コメントやシェアで教えてくださいね。
あなたの支援が、今日も誰かの笑顔をつくっています。