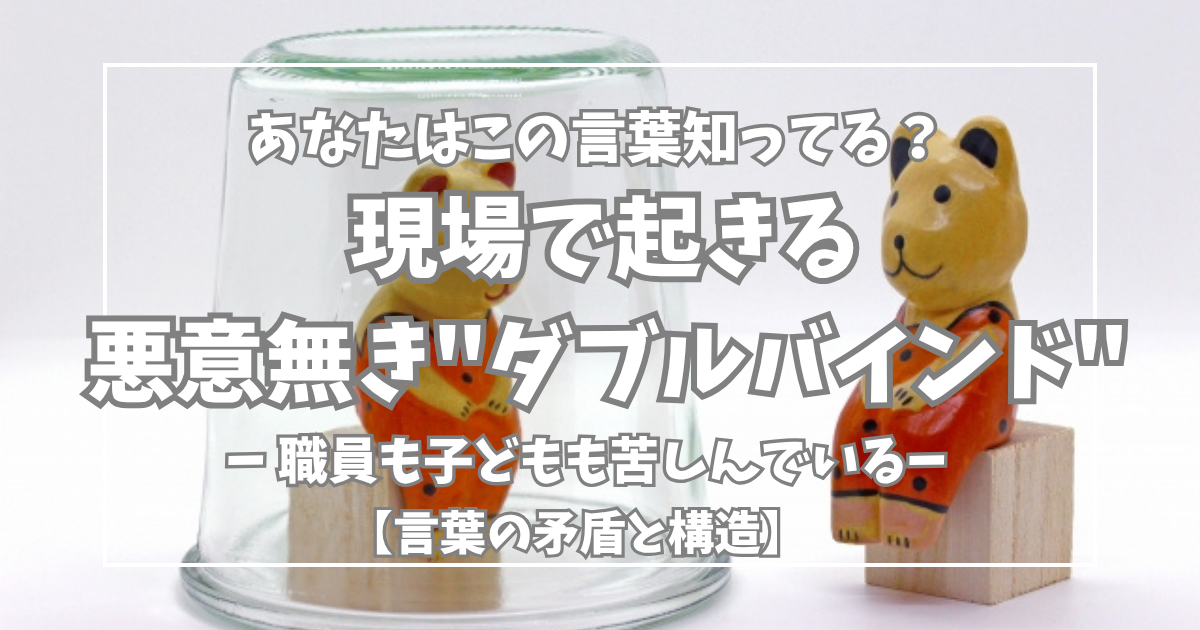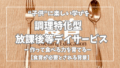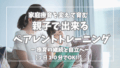1. はじめに:なぜ“ダブルバインド”を知る必要があるのか
放課後等デイサービス(以下「放デイ」)の現場では、職員が多くの役割を担い、児童一人ひとりの支援設計から環境調整、保護者・学校との連携まで、多岐にわたる対応を行っています。そのなかで、子どもが安心して活動できるようにという意図で支援を行っても、ふとした言葉・態度・組織の仕組みによって、児童が「どちらを選べばいいのだろう?」と迷ってしまう場面を見かけることがあります。
このような状態は、心理学で“ダブルバインド”(二重拘束)と呼ばれ、児童・職員双方にストレスや混乱をもたらす可能性があります。支援者として、ダブルバインドの構造を理解し、現場で起きそうな状況を見つめ、予防・対応することは、支援の質を保つうえで非常に重要です。

2. “ダブルバインド”とは何か? 理論的背景と支援現場の観点から
2.1 定義と起源
ダブルバインドとは、言語的メッセージと非言語的メッセージ、または異なる指示・期待が同時に提示され、どちらの選択をしても“間違っている”か“適合できない”という状況を指します。つまり、どちらを選んでも矛盾・葛藤・非肯定を引き起こす構造です。これは文化人類学者 グレゴリー・ベイトソン が1950年代に「精神病理との関連」で提唱した理論がその起源となっています。
支援現場で考えると、例えば“自分で考えなさい”と言われた後に“質問してはいけない”と言われる、など、矛盾するメッセージが同時に存在することで、受け手がどう行動してよいかわからず、思考・発言・行動を止めてしまう状態に陥ります。
2.2 実際に起こる構造:言語的メッセージ・非言語的メッセージの矛盾
例えば、職員が児童に「自分から手をあげて発言しようね」と言っておきながら、発言した際に「もう少し考えてから言いなさい」と遮ることがあります。言葉としては“発言を促す”が、実際の反応は“発言は控えめに”という非言語的・対応的メッセージになっている。児童からすれば「どうしたら正解なの?」という板挟みに感じてしまいます。
このような矛盾は、意図せず起こることが多く、職員の忙しさ・環境の変化・組織の仕組み・保護者・学校とのやり取りのなかで見落とされがちです。
3. 放課後等デイサービス現場におけるダブルバインドの具体的場面
3.1 職員‐児童間での指示と期待のズレ
放デイでは、児童が「積極的に活動に参加してほしい」と促される一方で、「静かに待っていようね」と促されるなど、活動参加と静観という二つの期待が混在する場合があります。児童は「どちらが正しいの?」と困惑し、結果的に発言・活動を控えたり、動きすぎて叱られたりという負の循環に入ることがあります。
例えば、「自由遊びしていいよ」と言われて外遊びを始めたら「あと10分で室内へ戻ろうね」と言われ、さらに「片付けを手伝ってね」と促される。児童にとっては“遊び・片付け・戻る”という複数のメッセージが短時間に重なり、「どれを優先すればいい?」という板挟みになります。
このような場面では、職員が意図を明確にして、児童の立場で「今はこの部分が優先だよ」と伝える必要があります。
3.2 児童‐保護者・学校との連携で生まれる板挟み状況
放デイでは、学校・家庭・支援施設それぞれから期待される役割が異なります。学校では「授業で集中しなさい」と言われ、家庭では「宿題を早く終わらせなさい」と言われ、放デイでは「自由にのびのび」「自分で決めて挑戦して」などと言われることもあります。
このように複数の場から矛盾するメッセージを受けている児童は、「つまりどうすればいいの?」という思考停止的な反応を示すことがあります。また、職員自身も「学校の方針に従うべきか」「家庭のニーズに従うべきか」「施設の理念を優先すべきか」というジレンマに陥ることがあります。
3.3 職員内・組織内での支援方針・評価基準の矛盾
職員が日々支援を行うなかで、「子どもを自主的に支援する」「学びを促す」「安全を守る」という複数の役割を兼務することが多いです。そして、施設運営・評価・保護者の満足度・行政報告・スタッフの稼働という複雑な構造のなかで、「もっとできることを探そう」「でも無理な負担をかけないように」といった矛盾したメッセージも出がちです。
例えば、「職員は子どもにたくさん話しかけてください」と指示されながらも、報告書を早く書くように促されている場合、職員はどちらを優先すればよいかわからず、双方が中途半端になってしまうことがあります。このような状況は、職員の疲弊・離職、支援の質低下につながりかねません。
4. ダブルバインドがもたらす影響:児童・職員双方の視点から
4.1 児童への影響
ダブルバインド状態が続くと、児童には以下のような影響が見られます:
- 自分の考えや発言を控えるようになる。自分の意思が大切にされないという経験が、自己肯定感を低下させます。
- 判断を保留して受け身になる。何をしても「良くない」と感じることで、思考停止状態に陥ることがあります。
- コミュニケーションの回避。矛盾を感じることで、発言や相談をしなくなり、助けを求められなくなる場合も。
これらは、発達障害・発達特性を持つ子どもにとって、特にリスクが高い状況と言えます。支援現場では「何をどう伝えているか」を丁寧に検証する必要があります。
4.2 職員への影響
職員側にも、ダブルバインド構造があると次のような負荷が生じます:
- 「支援すべき・でも制限もある」という矛盾した役割期待により、葛藤感や支援疲労を感じる。
- 指示・報告・評価の中で「どちらが正しいのか」という迷いが生まれ、判断力・モチベーションが低下。
- 子どもの反応が鈍かったり、支援の効果が見えにくくなることで支援者としての自己効力感が揺らぎ、離職やバーンアウトの要因となることもあります。
支援現場では、職員が矛盾構造に気づき、相談・振り返り・方針共有をする場を設けることが、支援の質維持・向上につながります。
5. ダブルバインドを回避・軽減するための支援設計とチーム文化
5.1 明確な指示・一貫したメッセージ設計
支援においては、メッセージがぶれないことが基本です。児童に向けて「自分で考えて行動しようね」と伝えたら、その後「言ったとおりじゃない」「もうちょっと待ってからね」と変化させないことが大切です。職員同士でも、支援方針・言葉遣い・対応基準を共通理解として持つことで、児童にとっても“どこがルールか”が明確になります。
また、指示・期待・反応が矛盾していないかを支援前に点検する時間を設けることが効果的です。
5.2 児童・職員・保護者・学校との対話と合意形成
支援は「施設が一方的に決める」ものではなく、児童・保護者・学校・職員が対話を通じて合意をつくることが重要です。特に、学校・家庭・施設間で期待や指示がずれていないかを定期的に確認することが、ダブルバインド発生の予防につながります。
例えば、保護者が「家では静かにしてほしい」と言い、学校では「もっと発言してほしい」と言い、施設が「自由に活動してほしい」と言ってしまうと、児童は三方向の矛盾の中で迷ってしまいます。対話を通じて「この時間は自由・この時間は発言」など、統一したメッセージを出す工夫が必要です。
5.3 フィードバック・振り返りの仕組みと見直し
活動後、職員ミーティングや振り返り会を定期的に持ち、児童がどのように受け取ったか、指示と反応にズレがなかったかをチェックすることが重要です。
- 「児童が混乱していた場面がないか」
- 「職員の指示に一貫性があったか」
- 「保護者・学校と伝えたことがぶれていなかったか」
こうした問いを持ち、改善策を具体的に出して実行に移す文化を育てましょう。
5.4 組織として矛盾を抱え込まない仕組み作り
施設運営・職員配置・評価制度・報告様式など、支援者を取り巻く組織構造にもダブルバインドの芽が潜んでいます。例えば、「児童の個別支援を深める」「でも定員枠を守って効率的に」という相反する期待が職員にかかることがあります。
このような構造的な矛盾を軽減するためには、施設が地域・行政・保護者と一体で「何を優先するか」「どのようにバランスをとるか」を明文化し、職員にわかりやすく共有することが必要です。悩みを抱え込む職員が出ないよう、相談窓口やメンタルケアの仕組みを整えることも有効です。
放課後等デイサービスで起こる“ダブルバインド”の典型例

① 児童への支援指示の矛盾
事例A:
「自由に遊んでいいよ」と言いながら、「静かにしてね」と伝える。
活動中、自由遊びをしてほしいという職員の意図と、他の子どもへの配慮から静かにしてほしいという思いが交錯します。
このように「自由にしていい」「でも静かに」という矛盾した指示は、子どもにとって「どうすればいいの?」という混乱を引き起こします。
改善の工夫:
「今日は室内遊びの時間なので、静かに遊べるおもちゃで遊ぼうね」と自由の範囲を具体化して伝える。
言葉の選び方ひとつで、子どもは行動を安心して選べるようになります。
② 職員への運営方針のダブルバインド
事例B:
「職員一人ひとりの個性を活かして支援してください」
と言われつつ、
「支援は全員同じ対応で統一してください」
とも求められる。
「個性の発揮」と「統一的対応」はどちらも正しい理念ですが、両立が難しい。
結果として、現場職員は「何を優先すべきか分からない」まま動きが鈍くなったり、他職員との間に摩擦が生まれたりします。
改善の工夫:
- 「支援の基本ルール(ベースライン)」と「個性を発揮してよい範囲」を明文化。
- 共有会で「この対応はどうするか」をすり合わせ、現場全体で共通理解を持つ。
放デイでは、この「すり合わせ」の時間を取ることがダブルバインドを防ぐ第一歩です。
③ 保護者・学校との期待のズレ
事例C:
学校:「もっと自立的に行動してほしい」
保護者:「無理をさせず、優しく接してほしい」
放デイ:「楽しく挑戦する場にしたい」
それぞれの立場で子どもへの期待が異なり、職員が板挟みになるケース。
どの意見も子どもを思ってのものですが、結果として「指導するべきか」「見守るべきか」の判断が難しくなります。
改善の工夫:
三者面談や情報共有シートを活用し、「子どもの目標を共有・段階的に統一」する。
「今は“挑戦期”」「今月は“安心期”」など、支援方針の時期的テーマを定めることで、期待のブレを減らせます。
ダブルバインドがもたらす心理的影響
児童への影響
- 行動の自発性が失われ、受け身になりやすい。
- 「何をしても叱られる」と感じ、自己否定感が強まる。
- 他者の感情を過剰に気にするようになり、不安・緊張が慢性化する。
特に発達特性を持つ子どもは「言葉通りに受け取る」傾向があるため、言語と態度のズレに敏感です。支援者は「どう伝わっているか」を意識する必要があります。
職員への影響
- 組織や上司の期待に板挟みになり、支援疲労・バーンアウトが起こりやすい。
- “正しい支援とは何か”が見えなくなり、支援方針がぶれる。
- チームの人間関係にも緊張が生まれ、ミスコミュニケーションが増える。
放デイ現場での「失敗からの改善」実例
ケース1:叱るタイミングのズレから学んだ職員チーム
状況
活動中に児童Aくんが他の子の玩具を取ってしまった。
ある職員は「今は自由時間だから少し様子を見よう」と考え、別の職員はすぐに注意をした。
Aくんは「さっきはいいって言われたのに、今はダメなの?」と泣き出してしまった。
問題分析
職員間で「自由時間における行動ルール」が共有されていなかったため、Aくんに矛盾した対応が伝わった。
改善
ミーティングで「自由遊びのルール」「即時対応すべき行動」「見守り優先の行動」を明文化。
以後、同様の混乱は大幅に減少。Aくんも「ルールが分かる」と安心して遊べるようになった。
ケース2:支援方針の違いで悩んだ新人職員の気づき
状況
新人のBさんは「子どもの自主性を大切にしたい」と考え、失敗しても見守る方針を取っていた。
しかし上司から「もっと指示を出して導いて」と言われ、混乱。Bさんは「どちらが正しいのか」と迷い、支援中に声かけのタイミングを失うことが多くなった。
改善
先輩職員とペア支援を行い、「介入」と「見守り」の基準を一緒に整理。
上司と話し合い、「安全確保が最優先」「学びの挑戦は次の段階」という段階的支援を導入。
Bさんは支援の軸を取り戻し、自信を持って関われるようになった。
ケース3:組織方針の曖昧さをチームで見直した例
状況
放デイCでは、管理者が「子どもの自主性を伸ばす支援」を方針に掲げていたが、
日々の記録では「指示を守れたか」「行動をコントロールできたか」といった評価が中心だった。
問題
理念(自主性)と実務(統制)が乖離しており、職員がどちらを重視すべきか分からなくなっていた。
改善
職員会議で「自主性とは何か」「支援で評価する項目は何か」を再定義。
“できた・できない”ではなく、“挑戦した・工夫した”を評価項目に変更。
結果、児童の活動参加率が上がり、報告書にもポジティブな記述が増えた。
ダブルバインドを防ぐ3つの実践ポイント
- 「伝える」ではなく「伝わる」を意識する。
言葉と態度・環境が一致しているかを常に確認する。 - “あいまいな善意”を整理する。
「優しさ」「自由」「見守る」は良い言葉ですが、意味を共有しないと矛盾を生みます。 - 矛盾を“気づきの種”として話し合う。
「ここ、少しズレていたね」と率直に話せるチーム文化が、信頼と成長を生みます。
6. 放デイで使える具体的実践チェックリスト
6.1 活動前/活動中の確認ポイント(児童視点)
- 活動の目的・ルールが児童にとってわかりやすい形で提示されていたか?
- 指示と期待が一貫していたか、矛盾はなかったか?
- 活動中に児童が「どっちをすればいいの?」という様子で固まっていなかったか?
- 支援者の言葉・態度・環境が、児童に安心・選択肢を感じさせていたか?
6.2 職員ミーティング・振り返り用チェック項目
- 本日の支援場面で、指示と反応にズレはなかったか?
- 保護者・学校・施設の三者で伝えているメッセージは一致していたか?
- 職員自身に「どちらも大切だけど矛盾していたな」と感じる場面はなかったか?
- 支援設計・指示を改善すべき点が見つかったか?具体的改善案は?
6.3 保護者・学校との共有ツール例
- 活動開始前の「今日のねらい・ルール」手紙・掲示
- 月末振り返りシート(児童の反応・指示に対する感想・改善提案)
- 三者面談時の「言われていること・やってほしいこと・困っていること」整理票
7. まとめ:矛盾を“支援改善のヒント”に変えるために

ダブルバインドは、決して“誰かが悪い”という問題ではなく、「支援・環境・組織・関係」が複雑に重なった構造的な問題と捉えることが大切です。そして、それを放置することは、児童・職員双方にとって支援機会の損失となりかねません。
支援現場で「どんな言葉・態度・ルールを出しているか」を振り返り、矛盾がないか、児童・職員双方が安心して動けているかを共に検討していくことで、支援の質が高まります。放デイの現場こそ、このような振り返り・対話・改善の文化を育てる場として重要です。
8. おわりに:まず一歩を踏み出そう
今日から、「言葉とメッセージがぶれていないか?」「児童が ‘どちらで動いたらいい?’ と感じていないか?」という視点を持って、日常的な支援を見つめ直してみてください。そして、職員同士、保護者・学校とも「どんなメッセージを出しているか」を共有し、矛盾を小さくしていきましょう。小さな改善の積み重ねが、児童にとって安心できる居場所と成長の機会を築きます。