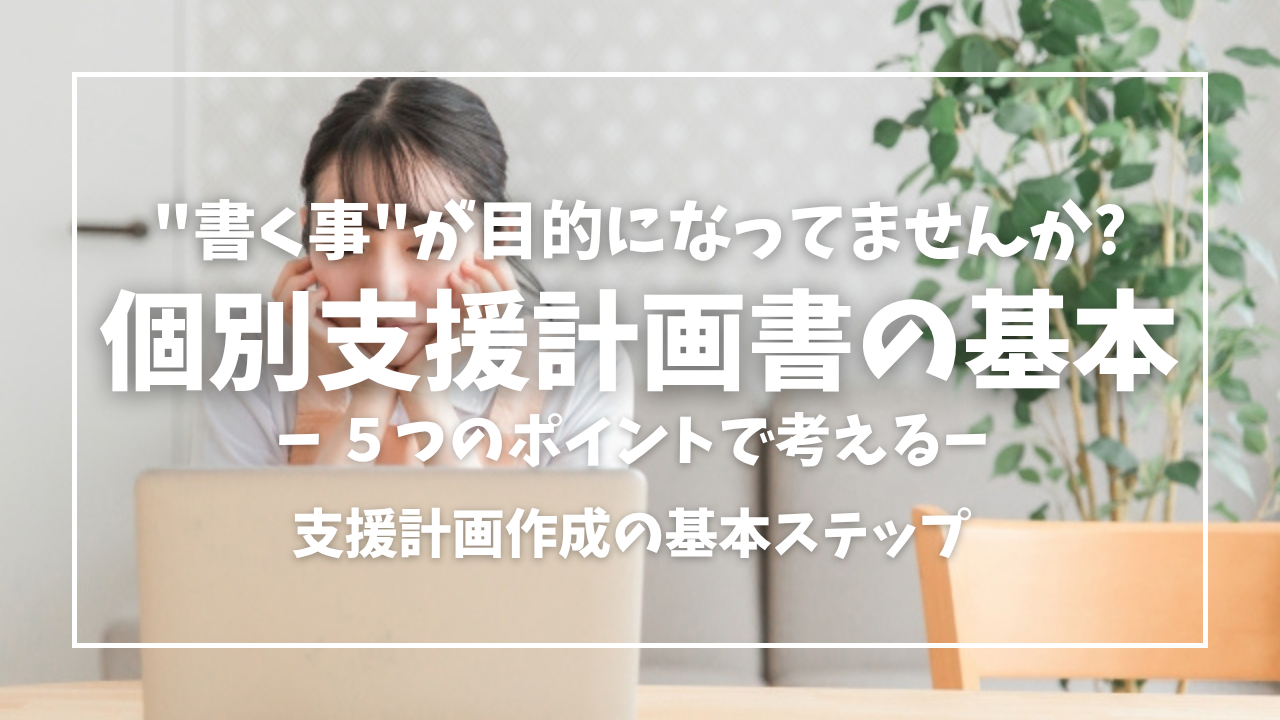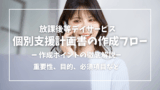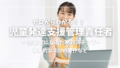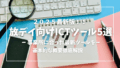はじめに:「書くこと」が目的になっていませんか?
個別支援計画の作成、「とにかく書かないと」になっていませんか?
本来、個別支援計画は子どもの支援をより良くするための“設計図”であり、「どう支援するか」をチームで共有するための大切なツールです。
この記事では、現場で役立つ実践的な「個別支援計画の書き方」を具体的にご紹介します。
個別支援計画とは?その目的と役割

個別支援計画とは、放課後等デイサービスで支援を行う際に必要な「子ども一人ひとりに合わせた支援の指針」を示した文書です。
役割は以下の3つ:
- 本人・保護者との共有(納得と安心のため)
- スタッフ間での支援方針の統一
- 実績報告や監査対応のための根拠資料
つまり、“現場で活きる”ことが第一です。
支援計画作成の基本ステップ
① アセスメント(事前情報収集)
保護者・本人からの聞き取り、学校からの情報、医師意見書などをもとに、本人理解の土台を築くステップです。
② 現状把握と課題整理
本人の強み・困り感・支援ニーズを「生活」「学習」「対人関係」などの視点で整理します。
③ 目標設定(長期目標・短期目標)
支援期間内に目指す到達点を「長期目標」、そこに向けた具体的ステップを「短期目標」として設定します。
④ 支援内容の明記
目標を達成するための支援内容(誰が・何を・どのように)を、日常業務に直結する形で具体的に記載します。
⑤ 評価と振り返りの流れ
計画終了時に評価を行い、次の目標へつなげていく。“書きっぱなし”にしないことが重要です。
支援計画で“外せない”5つのポイント
① 「本人中心」の視点
本人の思いや言葉、興味を反映させる。「大人目線の正解」だけにならないよう注意。
② SMARTな目標設定
具体的で測定可能な目標を。例:「5回中3回、他児と一緒にゲームを最後まで続ける」
③ 日々の支援とつながる内容
「現場でどう動くか」が見える記述に。支援が抽象的すぎると現場が迷います。
④ 記録しやすく、現場で使える言葉
形式的な表現よりも、現場のスタッフが読んですぐ理解できる内容・用語がベスト。
⑤ 法的・監査対応も意識する
期間、評価記録、関係機関との連携記録など、形式要件も必ずチェックしましょう。
よくあるNG例と改善策
- NG例:「人との関わりを増やす」→ 抽象的で評価できない
→ 改善:「週1回、2人以上での活動に5分以上参加する」 - NG例:「支援者が声をかけて様子を見る」→ 支援になっていない
→ 改善:「活動開始時、選択肢を提示して本人が選べるよう支援する」 - NG例:「特になし」→ 評価記録・振り返りが形骸化
→ 改善: 実際の変化を数値や行動で記録する
支援計画作成時に使えるテンプレ&質問例
【長期目標】
「〇ヶ月以内に、〇〇ができる状態を目指す」
【短期目標例】
- 週2回、スタッフと一緒に宿題に10分以上集中する
- 5分間の着席が週3日継続できるようになる
【質問例(アセスメント用)】
- 今できること・困っていることは何ですか?
- 子どもが今興味を持っているものは?
- 家庭での様子や、支援に期待することは?
よくある質問(Q&A)
Q. 計画は何ヶ月に一度書けばいいの?
→ 原則、6ヶ月に1回(年2回)。途中変更があれば都度更新も可能です。
Q. 学校との情報共有は必須ですか?
→ 必須ではありませんが、支援の質を高めるためには望ましいです。
Q. 計画に保護者の同意は必要ですか?
→ はい。面談を通じて説明・同意を得た上で計画書を交付します。
まとめ

個別支援計画は、「支援の質」を決める最も重要なツールです。
- 書くことが目的化しないように
- 現場で“読まれる・使われる・改善される”内容を意識する
- 子どもと保護者の声を反映し、「成長の軌跡」を描く設計図として活用しましょう
CTA(行動喚起)
「今書いている支援計画、現場で使われていますか?」
一度立ち止まって見直すことで、支援の質とスタッフのやりがいが大きく変わるかもしれません。
まずは1人のお子さんから、“伝わる計画”を書いてみてください。