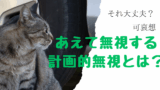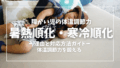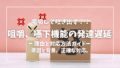1. はじめに:なぜ“つば吐き・つば塗り”が問題視されるのか?
発達障がいの子ども(ASDなど)に見られる「つば吐き」「つば塗り」は、衛生面・人間関係面でトラブルを引き起こします。ただし、この行動は注目獲得や逃避など何らかの“目的”を伴う不適応行動であり、叱って対処することは逆効果になるケースがあります 。
2. つば吐き・つば塗りの背景・原因を徹底分析

✳ 注目行動になっている
大人や周囲が大きく反応すると、子どもにとっては「意味ある行動」に転化し、強化されます 。
✳ 逃避行動の一種
自分の意思が通らない、ストレスを強く感じる場面で、“つば吐き”でその場を一時的に離れようとする行動と捉えることもできます 。
✳ 感覚刺激欲求
一部の子どもには、“唾液の感触”や“口周りの感覚”を楽しむ(感覚遊び)欲求があり、つば吐きに至るケースがあります。
3. 支援者・保護者として取り組むべきステップ
放課後等デイのコアスタッフが同じ対応を継続することで、効果的な支援ができます。
3.1 原因の「丁寧な特定」
つば吐きが発生する場面を正確に記録し、「環境要因」「触発要因」「機能的な目的」を分析します 。
3.2 大人が“過度に反応しない”対応
叱ったり注目すると行動が強化されるため、無視・スルーすることが最初の対応です。
3.3 代替行動の指導
つば吐きへの代替として、以下の落ち着く行動を一緒に練習します:
- ガムや唾液抑制用具(マスク、吸い口付きボトル)の使用
- 深呼吸、タッチで意思表現するなどのクールダウン行動 。
3.4 環境整備
刺激の少ない場所へ移動、机に塗りつけないようにビニールカバーを設置など物理的な環境調整が有効です。
3.5 正しい行動を積極的に強化
「ティッシュで口を拭けた」「ガムに口が向いた」など、代替行動ができたら即座にほめ、報酬を準備します。
4. 物理的・道具的対策の具体例
- マスク/唾液吸収パッド:唾が飛び出ないようにします。
- 手袋着用環境:塗りつけ不可能な状態をつくる 。
5. スタッフ間・家庭との連携体制づくり
- 放課後等デイだけでなく、家庭や登校先とも対応を統一し、「スルー+代替行動+強化」の一貫した支援を継続します 。
- スタッフ間で記録・情報共有し、誰がどの対応をしたか把握できるようにしましょう。
6. チェックリスト:対応の具体的ステップ
- 起こる場面・頻度・時間帯を記録
- 子どもに注目せず、冷静にスルー
- 代替行動(ガム、吸い口付き道具、深呼吸)を習慣に
- 環境調整(静かな場所、除菌カバー、手袋)を実施
- 正しい行動ができたら即ほめ・シールなどで褒める
- 家庭や学校と対応ルールの共有・統一
- 月に1回程度は支援会議で振り返りを実施
✅ まとめ:つば吐き対応で迷わない支援フロー
- つば吐き行動は「注目」「逃避」「感覚欲求」のいずれかを目的としています
- 「叱る」は逆効果!反応せず、スルーが基本
- 行動の代わりになる“落ち着き行動”を一緒に練習
- 環境を物理的・道具的に整備する
- スタッフ・家庭・学校で対応を統一し、継続的に強化していく
📌 最後に

「つば吐き・つば塗り」は、単なる迷惑行動ではなく、子どもの気持ちが現れた行動です。対応は叱るのではなく、原因理解・環境調整・代替行動の導入・行動強化を軸にすると確実に改善に導けます。放課後等デイスタッフとして、ぜひチームで取り組んでいってください。
出典URL 強度行動障害対応PDF