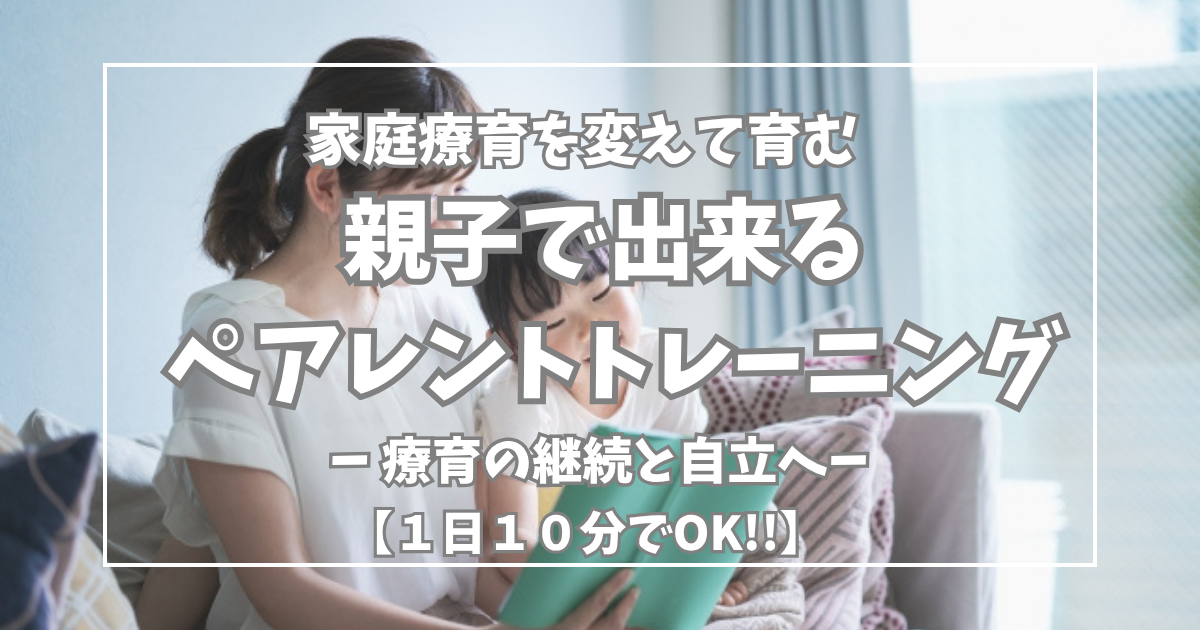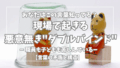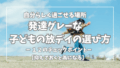1. はじめに:療育の「継続」と「自立」を家庭へ
ペアレントトレーニング(PT)は、親が子どもの療育を家庭で実践できるよう支援するプログラムで、1960年代米国発祥、日本でも自治体や医療機関・NPO等で導入が進んでいます。家庭という「生活の場」を療育の実践現場にすることで、支援の継続性と質が劇的に向上します。
2. ペアレントトレーニングの目的と効果

✔ 保護者にとって
- 子どもの行動背景を理解し、対応スキルを習得 → ストレスや抑うつ傾向が軽減。
- 一貫した対応ができるようになり、家族全体の安心感が増します。
✔ 子どもにとって
- 問題行動の減少、自己調整力の向上、コミュニケーション力の改善。
- 自閉症スペクトラムやADHDの場合、家庭での日常スキルが確実に向上するというエビデンスがあります。
3. ペアレントトレーニングの構成とやり方
日本ではグループ型が主流で、90~150分×5~10回が一般的です 。厚労省マニュアルでは「講義+ロールプレイ+宿題+振り返り」のサイクルが基本。
コア要素(6つの柱)
- 子どものよい行動を見つける
- 行動を3タイプに分類
- 理解→意味を考える
- 環境調整
- わかりやすい指示の出し方
- 不適切行動への対応方法
4. 支援者・保護者・家庭の連携フロー
- ニーズ把握:保護者との面談で困りごとや目標を整理。
- 講義・ワーク:PT支援者が対話・ロールプレイで処理方法を学習。
- 家庭実践:宿題として日常に取り入れ、変化を記録。
- 振り返り:次講座で共有し、支援方法を調整。
- フォローアップ:定期的に再確認し改善。スタッフ・家庭・関係機関で一貫支援を継続。
5. 家庭で即実践できるスキルと具体例
✔ 行動の分類・ABC分析
子どもの行動を「好ましい/好ましくない/危険」へ分類し、Antecedent(先行)→ Behavior(行動)→ Consequence(結果)を分析。
✔ 正の強化(褒め方の工夫)
行動直後に視線・声かけ・拍手・ごほうびなどで肯定的に強化。
✔ 上手な無視
好ましくない行動には反応せず、行動が減ったら好ましい行動をほめる。
✔ 指示の出し方
Calm(穏やか)・Close(近くで)・Quiet(静かな声)で伝え、子どもが従えばすかさず褒める。
✔ 環境調整
危険・混乱因子を減らし、成功体験を得やすい環境を整備。
6. 実践例:3つの家庭場面
🏫 実践例①:登校渋りへの対応
- 課題:朝の準備を嫌がる
- 対応:視覚スケジュール+小さな成功体験と具体的褒め
- 結果:準備がスムーズになり、自信がついた
🍽️ 実践例②:食事場での落ち着きづくり
- 課題:食卓を去ってしまう
- 対応:タイマー導入+座り続けたらすぐ褒め
- 結果:集中時間が延び、精神的不穏も軽減
📚 実践例③:宿題への嫌悪感
- 課題:宿題への集中が続かない
- 対応:課題を小分けにし、休憩と報酬入りのスケジュール管理
- 結果:集中時間が伸び、取り組みへの抵抗感が減少
7. 放課後等デイサービスでの導入ポイント
▶ スタッフ研修
児発管や支援員へABC分析・CCQなどの基礎知識を研修し、家庭との連携窓口を育成。
▶ 模擬セッションの実施
事業所内で実践的なワークやロールプレイを用意し、保護者の参加を促す。
▶ 関係機関との協同
発達支援センターや医療機関と連携し、家庭・学校・通所支援で一貫性あるアプローチを設計。
✅ まとめ|実践チェックリスト
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1 | 保護者の相談・困りごとを整理 |
| 2 | 講義&ロールプレイで家族と学び合い |
| 3 | 宿題として家庭実践 → 記録・振り返り |
| 4 | 正の強化・無視・CCQ・環境調整のスキル活用 |
| 5 | 成功例をチームで共有・連携調整 |
| 6 | 軌道に乗ったらフォローアップ実施 |
🔚 最後に

ペアレントトレーニングは、家庭という「日常」の中に療育を根づかせる支援手段です。放課後等デイサービスはPTの導入ハブとして、家庭・専門家・学校との連携を促進できます。「一日10分の工夫」が、子どもの自信と安心を育て、家族全体の暮らしを豊かにします。まずは一歩、家庭支援を始めてみませんか?